「防災 9月」と検索するあなたは、9月1日の「防災の日」や、この月に集中して行われる防災訓練の意味について疑問を持っていませんか?
実は、9月が防災強化の月とされている背景には、1923年の関東大震災という未曾有の災害と、台風の多い季節性という2つの要因があります。
本記事では、「防災とは何か?」という基本から、「なぜ9月1日が特別な日なのか」、そして「防災週間」や「年間の防災関連日」など、知っておきたい制度や背景を丁寧に解説します。
また、10月・11月・1月・3月にも行われている防災の取り組みや、防災イベント・キャンペーン情報も網羅的に紹介。
さらに、行政や企業が季節ごとに実施する実践的な防災活動についても触れており、通年で備えるためのヒントが満載です。
防災を「特別な日」だけのものにせず、日常に根付かせたいあなたにこそ読んでほしい内容です。
記事のポイント
9月が防災の月とされる由来や歴史を理解できる
関東大震災から学ぶ防災の重要性を把握できる
年間の防災関連日や訓練の時期を知ることができる
行政や企業の季節別防災活動の内容がわかる
9月が防災の月とされる理由とは?
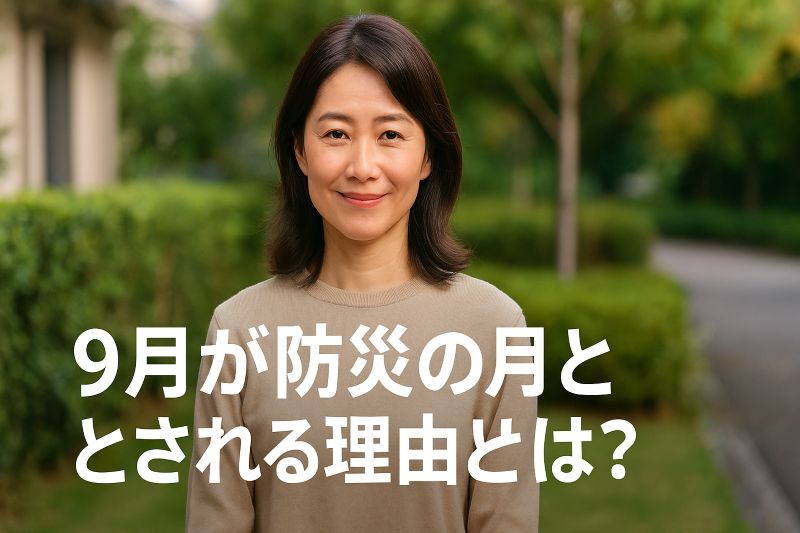
のいぼうラボ イメージ
この章では、9月が「防災の月」とされる歴史的背景や制度の成り立ちについて解説します。関東大震災や防災週間の由来を知りたい方はぜひ参考にしてください。
ポイント
- 防災とは何ですか?
- なぜ9月1日が特別な日なのか
- 1923年の大地震とその教訓
- 9月に防災訓練が多いのはなぜ?
- 防災週間の目的と背景
防災とは何ですか?

のいぼうラボ イメージ
「防災とは何ですか?」と疑問に感じて検索する方は多くいます。
9月の防災月間や学校・職場での訓練を前に、正しい定義や背景を知っておくことは非常に重要です。
要点まとめ
防災とは「災害を防ぎ、被害を最小限に抑えるための行動全般」
予防・応急・復旧の3つの段階がある
国や自治体、企業、個人のレベルで取り組まれている
9月の防災月間は防災意識を高めるために制定された
防災とは「地震・台風・火災・津波などの自然災害や事故による被害を防ぎ、または被害を最小限に抑えるための計画や対策を行うこと」です。
この言葉には、「事前の備え」と「災害発生時の行動」、「復旧・再建」までを含む幅広い意味があり、私たちの日常生活や社会インフラと密接に関わっています。
例えば、住宅の耐震補強や、非常持ち出し袋の準備、防災訓練への参加などが防災行動の一例です。
また、行政が作成するハザードマップや避難計画、企業の事業継続計画(BCP)なども、防災の一環として重要です。
このように防災には以下の3段階があります:
予防段階(例:避難所の整備・防災教育)
応急対応段階(例:災害時の避難・安否確認・応急手当)
復旧段階(例:被災地の復旧、ライフラインの再建)
防災は一部の専門家や自治体だけが行うものではありません。
個人の行動や家庭での備えが、命を守る大きな要素になるため、誰もが主体的に取り組む必要があります。
ただし、注意点として、防災意識が高まるのは災害後になりがちです。
災害が「起こる前」の行動が最も重要であることを理解し、「その時になってから」では遅いという認識が求められます。
FAQ
Q:災害対策と防災は同じ意味ですか?
A:似ていますが少し違います。災害対策は被害を減らす具体的な取り組み、防災はそれを含むもっと広い概念です。
出典リスト
転倒防止ワイヤーが搭載されて、停電時でも常温の水を出せます。
停電が起こった時、非常電源として効果的です。
\防災応援キャンペーン/【★楽天1位★】簡易トイレ プライバシーテント 災害用 防災グッズセット 処理袋付き 軽量 折りたたみ 洗える 耐荷重150kg
ソーラーモバイルバッテリー 大容量 22.5W/PD18W 63200mAh 急速充電 ソーラーチャージャー 6台同時充電 3本ケーブル内蔵+USBポート 5way蓄電 IPX7防水 高輝度 LEDライト付き
なぜ9月1日が特別な日なのか

のいぼうラボ イメージ
「なぜ9月1日が特別な日なのか」という疑問は、防災月間の由来や歴史に深く関係しています。
この日は単なるカレンダー上の記念日ではなく、日本の災害史と強く結びついています。
要点まとめ
9月1日は「防災の日」として1959年に制定
1923年9月1日の関東大震災がきっかけ
台風・地震などの災害対策を呼びかける象徴的な日
毎年この日を中心に防災週間が実施されている
9月1日が特別な日とされているのは、この日が日本で最大級の自然災害の一つ「関東大震災」の発生日だからです。
加えて、この日は年間を通じて台風が接近・上陸しやすい時期と重なることも理由の一つとされています。
この背景から、政府は1959年に9月1日を「防災の日」と定めました。
目的は、過去の災害を教訓にし、国民一人ひとりが防災意識を高め、命を守る行動をとれるようになることです。
例えば、1923年9月1日に発生した関東大震災では、震源が東京・神奈川を直撃し、死者・行方不明者合わせて10万人以上の被害が出ました(出典:気象庁 関東大震災)。
この教訓から「災害は突然やってくる」という意識が国民の中に根づくきっかけとなったのです。
このため、9月1日は単なる記念日ではなく、「備えることの重要性」を思い出す日として意味を持っています。
また、9月1日から始まる「防災週間」では、各自治体や企業、学校で防災訓練やイベントが開催されるため、実際に行動につなげやすい機会にもなっています。
ただし、問題点として「形式的に終わってしまう防災訓練」や「家庭での備えが十分にされていない現実」もあり、本質的な備えが日常化されていない課題も残されています。
FAQ
Q:9月1日が防災の日なのはなぜ?
A:1923年に関東大震災が起きた日であることと、台風シーズンに備える意味もあるからです。命を守る行動を考えるきっかけとして制定されました。
出典リスト
1923年の大地震とその教訓

のいぼうラボ イメージ
「1923年の大地震とその教訓」は、日本の防災意識の原点とも言えるテーマです。特に9月1日が防災の日として認定されている背景を理解する上で、避けて通れない出来事です。
要点まとめ
1923年9月1日、関東大震災が発生
死者・行方不明者は10万5千人以上(出典:気象庁)
都市火災と通信インフラの崩壊が被害を拡大
これを教訓に防災政策が本格化
教育・訓練・備蓄の重要性が再認識された
1923年の大地震、すなわち「関東大震災」は、日本の災害対策史においてもっとも重大な転機の一つです。
この地震から得られた教訓は、現代の防災政策や訓練制度にも大きく影響しています。
その理由は、地震そのものの規模だけでなく、都市火災・避難混乱・通信遮断などの「複合的被害」が社会に甚大な影響を与えたためです。
たとえば、1923年9月1日午前11時58分、相模湾北西部を震源とするマグニチュード7.9(推定)の地震が首都圏を襲い、死者・行方不明者は推定105,000人以上とされています(出典:気象庁 関東大震災)。
この地震によって得られた教訓の一つは、「地震直後の二次災害(火災やパニック)への対策の必要性」です。
多くの建物が木造だった当時、各所で火災が発生し、逃げ遅れによる被害が多数発生しました。
また、被災直後には通信網・鉄道・道路が寸断され、正確な情報が届かず混乱が拡大しました。
こうした教訓から、政府は地震・津波・火災に備えた「複合型の防災対策」を強化する方向へと進みました。
学校や地域における防災教育、初期消火の訓練、防災ラジオの普及などは、この大震災の経験に基づく対策です。
一方で、当時の対応には限界も多く、復旧までに数年を要しました。
このことから「平時の備え」がいかに重要であるかが広く認識されるようになり、現在の防災週間や防災訓練のルーツにもつながっています。
このように、1923年の関東大震災は「防災を後回しにしない」という社会的価値観を築いた原点であり、現代においても忘れてはならない教訓といえるでしょう。
FAQ
Q:関東大震災の教訓って、今でも生きているの?
A:はい。学校での避難訓練や、企業の事業継続計画(BCP)など、現在の制度や教育に数多く反映されています。
出典リスト
9月に防災訓練が多いのはなぜ?

のいぼうラボ イメージ
「9月に防災訓練が多いのはなぜ?」という疑問は、毎年恒例の地域訓練や企業研修に参加している人ほど気になるテーマです。
実はこの時期に集中するのには、明確な背景と制度上の理由があります。
要点まとめ
9月1日は「防災の日」として公式に制定されている
毎年8月30日~9月5日は「防災週間」
関東大震災の発生日にちなむ象徴的意味合い
台風シーズンと重なるため実効性が高い
政府や自治体による訓練実施が推進されている
9月に防災訓練が多く実施される理由は、「制度として定められた防災週間」と「災害リスクの高い時期が重なる」ためです。
まず、9月1日は内閣府が定めた『防災の日』です。
これは、1923年の関東大震災の教訓を忘れず、防災意識を高めることを目的として1959年に制定されました(出典:内閣府)。
これに伴い、毎年8月30日から9月5日までの1週間は「防災週間」として、全国の自治体・企業・学校などで訓練や啓発イベントが集中的に行われています。
具体的な例としては、自治体による大規模避難訓練、小中学校での地震避難訓練、企業での安否確認システムのテスト運用などがあり、実際の災害を想定したシミュレーションが行われます。
特に首都圏では、東京都の「帰宅困難者対策訓練」などもこの時期に集中します(出典:東京都防災ポータル)。
また、9月は気象庁が発表する台風の接近・上陸のピークと重なるため、現実的な災害対応訓練としてのタイミングも適しています。
災害の発生確率が高い時期に訓練を行うことで、緊張感と実効性のある教育効果が期待できるのです。
一方で、形骸化した訓練や、想定に偏りすぎた内容に陥ると、かえって「防災疲れ」や「現実離れした対応」に繋がるおそれもあります。
そのため、実施側は「参加者の行動変容」を意識し、最新のハザードマップや地域特性を反映させた現実的な内容にすることが望まれています。
FAQ
Q:9月以外に訓練をしてはいけないの?
A:いいえ、年間を通じて訓練は可能です。ただし、国の防災週間と重なる9月は、予算や人員が確保しやすく、多くの組織がこの時期に集中させているのです。
出典リスト
出典:内閣府 防災週間
出典:内閣府 防災の日の由来
防災週間の目的と背景

のいぼうラボ イメージ
「防災週間の目的と背景」を理解することは、なぜ9月に全国で防災訓練が集中するのかを知るために欠かせません。
制度的な意味と歴史的経緯を知ることで、自分ごととして防災を考えるきっかけになります。
要点まとめ
防災週間は毎年8月30日~9月5日に実施
制定の背景は関東大震災の教訓
目的は防災意識の普及・訓練の実施促進
国・自治体・企業・学校などが参加
公的機関主導の全国規模のキャンペーン
防災週間は、毎年8月30日から9月5日までの1週間に実施される、全国規模の防災啓発活動期間です。
この週間の目的は、自然災害に対する備えの大切さを広く社会に伝え、防災訓練や知識の共有を通じて、災害時における対応力を高めることにあります。
制定の背景には、1923年9月1日に発生した関東大震災の教訓があります。
甚大な被害を出したこの地震を忘れず、再発防止・被害軽減を目指す取り組みとして、1959年に「防災の日」が設けられ、その前後1週間が防災週間となりました(出典:内閣府 防災情報)。
この防災週間には、国・自治体・企業・学校などのあらゆるレベルの組織が参加し、地震や風水害を想定した訓練やシンポジウム、展示会、オンラインイベントなどが実施されます。
また、企業では事業継続計画(BCP)や従業員の安否確認訓練などが、この週間に合わせて集中的に行われ、災害時の業務継続能力の向上に寄与しています。
学校教育においても、避難経路の確認や地域の防災施設見学など、体験を通じた教育が実施されます。
一方で、注意点としては「形だけの訓練」で終わってしまうケースがあることです。
本質的な行動変容を促すには、リアリティのある訓練設計や、家庭・個人の備えを見直す機会として防災週間を活用する意識が必要です。
FAQ
Q:防災週間って一般の人も参加できますか?
A:はい。自治体や企業の訓練・イベントは多くが一般公開されています。特設サイトでスケジュールが案内されることもありますので、事前確認をおすすめします。
出典リスト
9月以外にもある防災の意識啓発の日

のいぼうラボ イメージ
この章では、年間を通じて設けられている防災関連の記念日や啓発活動について紹介します。9月以外にも防災を意識したい方に役立つ情報です。
ポイント
- 年間で設定されている防災関連日とは?
- 10月・11月にもある防災の取り組み
- 1月や3月の防災月間の特徴
- 行政・企業による季節別の防災活動
- 防災イベントやキャンペーン情報も要チェック
- 9月はなぜ「防災の月」なのか?のポイント!
年間で設定されている防災関連日とは?
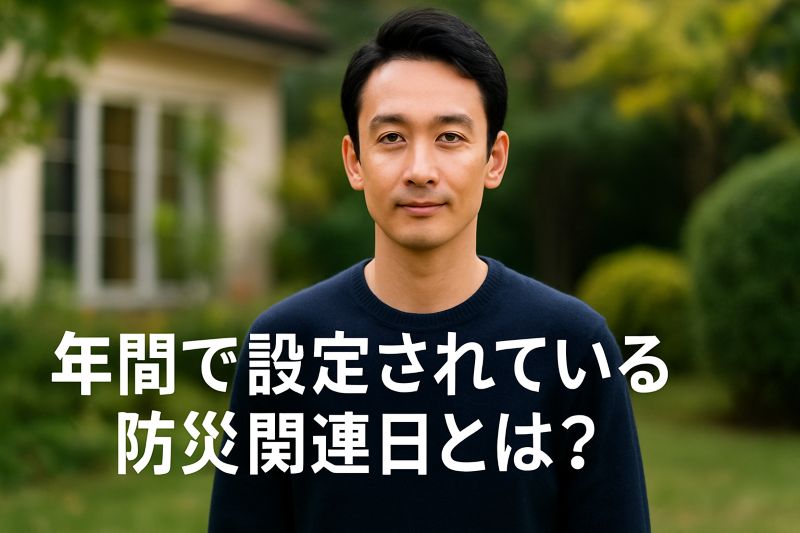
のいぼうラボ イメージ
「年間で設定されている防災関連日とは?」という疑問は、防災の日(9月1日)だけでなく、通年で防災を意識するための情報を探している読者にとって重要です。
各月にある防災に関する記念日や啓発日を知ることで、防災意識を持続的に高めることができます。
要点まとめ
防災に関する記念日は年中複数設定されている
9月1日(防災の日)以外にも、1月、3月、10月、11月、12月に防災関連日が存在
地震・津波・風水害・国際連携など多様なテーマに対応
学校・企業・自治体が各月に応じて啓発活動を展開
防災意識を高めるための啓発日は、9月1日の「防災の日」だけではありません。
実は日本には、年間を通じて複数の「防災関連日」が設けられており、それぞれ異なる災害や課題に焦点を当てています。
このような記念日は、国の機関や地方自治体、国際機関の協力をもとに定められており、防災教育・訓練・広報活動のきっかけとなる重要なタイミングです。
以下に代表的な防災関連日を月ごとにまとめます。
年間の防災関連日一覧
| 月 | 防災関連日 | 概要 |
|---|---|---|
| 1月 | 1月17日:防災とボランティアの日 | 阪神・淡路大震災(1995年)を教訓とし、地域防災とボランティアの重要性を再確認する日 |
| 3月 | 3月:防災月間(企業・自治体主導) | 東日本大震災(2011年)の記憶を風化させず、備えを見直す取り組み |
| 9月 | 9月1日:防災の日 | 関東大震災の教訓を忘れず、国民の防災意識向上を目指す |
| 10月 | 10月13日:国際防災の日 | 国連が定めた国際的な防災意識向上デー。世界規模の啓発活動が行われる |
| 11月 | 11月5日:津波防災の日 | 1854年の安政南海地震と「稲むらの火」にちなむ津波防災の啓発日 |
| 12月 | 12月1日:地域防災の日(自治体による制定) | 冬季の火災や雪害などに備えた地域防災強化の期間 |
このように、年間を通してさまざまな防災に関する日が定められている背景には、「単発のイベントで終わらせず、通年で防災意識を維持してもらいたい」という狙いがあります。
一方で、課題としては「日常生活との接点が少なくなりがち」な点です。
記念日があること自体を知らない人も多いため、行政や企業がSNSや地域メディアを活用して周知を強化する取り組みが求められています。
FAQ
Q:防災の日は9月だけじゃないんですか?
A:いいえ、1月・3月・11月などにも防災をテーマにした記念日があります。それぞれ異なる災害の教訓や目的があります。
出典リスト
転倒防止ワイヤーが搭載されて、停電時でも常温の水を出せます。
停電が起こった時、非常電源として効果的です。
\防災応援キャンペーン/【★楽天1位★】簡易トイレ プライバシーテント 災害用 防災グッズセット 処理袋付き 軽量 折りたたみ 洗える 耐荷重150kg
ソーラーモバイルバッテリー 大容量 22.5W/PD18W 63200mAh 急速充電 ソーラーチャージャー 6台同時充電 3本ケーブル内蔵+USBポート 5way蓄電 IPX7防水 高輝度 LEDライト付き
10月・11月にもある防災の取り組み

のいぼうラボ イメージ
「10月・11月にもある防災の取り組み」は、防災の日(9月1日)に限らず、年間を通じて防災意識を高めたいと考える人にとって注目すべき内容です。
特にこの2か月には、国際的・歴史的背景に基づいた重要な啓発日が設けられています。
要点まとめ
10月13日は「国際防災の日」(国連制定)
11月5日は「津波防災の日」(日本政府制定)
国・自治体・国際機関による啓発イベントや防災訓練が行われる
歴史的災害や国際的枠組みをもとに制定された記念日
防災意識の「継続」に寄与する取り組み
10月と11月にも、9月と同様に重要な防災関連の取り組みが実施されています。
これらの時期は防災週間ほどの知名度はないものの、それぞれ異なる目的と背景を持ち、国内外で注目されている活動です。
まず、10月13日は「国際防災の日(International Day for Disaster Risk Reduction)」です。
これは国連(UNDRR)が定めた記念日で、世界各国が協力して自然災害のリスク軽減に向けた取り組みを促進することを目的としています。
この日には、国際シンポジウム、パネル展示、SNS啓発キャンペーンなどが行われ、日本国内でも地方自治体やNPOなどが関連イベントを開催します。
特に災害が頻発するアジア太平洋地域において、この記念日は「防災は国境を越える課題」であることを認識する良い機会とされています(出典:国連広報センター)。
次に、11月5日は「津波防災の日」です。
これは1854年に発生した安政南海地震と、それに伴う津波から住民を救った逸話「稲むらの火」に由来しています。
この教訓を未来に伝えるべく、2011年に日本政府が制定しました。
毎年この日を中心に、沿岸地域を中心とした津波避難訓練、防災教育、デジタル教材の配信などが実施され、子どもから高齢者まで幅広い層に防災の意識を浸透させる取り組みが続けられています(出典:津波防災の日 特設ページ)。
こうした取り組みの価値は、9月だけでなく「継続的に災害への備えを意識できる」という点にあります。
ただし、防災月間以外の訓練や広報活動はメディア露出が少ないため、個人や家庭が意識して情報を取りに行く姿勢も重要です。
FAQ
Q:10月・11月の防災の日って、一般の人にも関係ありますか?
A:はい。自治体が主催する訓練や講座は誰でも参加できるものが多く、防災意識を深める良い機会になります。
出典リスト
1月や3月の防災月間の特徴

のいぼうラボ イメージ
「1月や3月の防災月間の特徴」は、9月以外の時期にも災害リスクが高まる日本において、継続的な防災意識の醸成に不可欠なテーマです。
特に冬季や震災の記憶が色濃い春先は、防災強化の節目とされる傾向があります。
要点まとめ
1月17日は「防災とボランティアの日」
3月は「防災月間」として民間・自治体が自主的に実施
阪神・淡路大震災・東日本大震災の教訓がベース
災害への風化防止と備えの見直しを目的としている
寒冷期特有の災害(火災・雪害)への対応も意識
1月と3月は、9月の「防災の日」とは異なる視点で防災を考える大切な機会です。
この時期に防災月間が設定されている背景には、それぞれ大規模な震災の記憶と、季節特有のリスクに備える必要性があります。
まず、1月は「防災とボランティアの日」(1月17日)を中心に活動が広がります。
この日は、1995年に発生した阪神・淡路大震災の教訓をもとに制定されました。
震災直後に多くの市民ボランティアが現地に駆けつけたことから、地域の連携や共助の重要性を見直す契機として位置づけられています。
この時期には、内閣府や自治体主導でシンポジウム・パネル展示・訓練が行われるほか、学校や福祉施設などでは地域との連携をテーマにした防災教育も活発に行われています(出典:政府広報 防災とボランティアの日)。
一方で、3月は「自主的な防災月間」として多くの団体が独自の活動を展開しています。
これは、2011年3月11日に発生した東日本大震災の記憶を風化させないための啓発月間として、企業・学校・自治体などが連携して設けたものです。
この期間には、津波避難訓練、ライフライン遮断を想定したシミュレーション、防災用品の見直しなどが行われ、「自分と家族を守る」視点での取り組みが重視されます。
3月は年度末というタイミングでもあるため、業務計画や家計・生活の見直しと合わせて「防災の棚卸し」を行うのに最適な時期でもあります。
また、冬から春にかけては乾燥・強風による火災、雪崩や凍結事故など、寒冷期特有の災害にも注意が必要です。
このため、1月・3月の防災啓発では「火の元管理」や「雪害対応」も併せて取り上げられています。
ただし、課題としては「9月に比べて周知力が弱い」点が挙げられます。
多くの人が防災月間といえば9月を思い浮かべるため、1月・3月の取り組みを効果的に浸透させるためには、メディアやSNSを活用した広報活動の強化が求められています。
FAQ
Q:1月や3月の防災月間って誰が決めているの?
A:1月17日は政府が定めた記念日ですが、3月は主に自治体や企業が東日本大震災の教訓を踏まえて独自に行っている活動です。どちらも目的は「防災意識の継続」です。
出典リスト
行政・企業による季節別の防災活動

のいぼうラボ イメージ
「行政・企業による季節別の防災活動」は、年間を通じて防災意識を持続させるために欠かせない取り組みです。
災害の種類は季節ごとに変化するため、それに対応する形で柔軟に対策が講じられています。
要点まとめ
季節ごとに災害リスクが異なるため、対策内容も変化
春:火災・黄砂・雪解け水害への備え
夏:台風・豪雨・熱中症リスク対策が中心
秋:地震・土砂災害・停電対応の訓練実施
冬:積雪・凍結事故・火災への備えと啓発
行政は訓練・避難情報の強化、企業はBCPや設備点検を実施
行政や企業が実施する「季節別の防災活動」は、年中変化する自然災害に応じた対策を講じることで、リスクを軽減し、被害の最小化を図るものです。
この背景には、日本が地震・台風・雪害・火山など多種多様な災害に見舞われる国であり、災害リスクが季節によって大きく異なるという特徴があります。
ここで、季節ごとの主な防災活動を簡単に整理してみましょう。
季節ごとの防災活動の例
| 季節 | 主なリスク | 代表的な対策 |
|---|---|---|
| 春 | 火災、黄砂、雪解けによる洪水 | 消火設備点検、河川監視、黄砂対策マスク配布 |
| 夏 | 台風、集中豪雨、熱中症 | 防災無線訓練、水害マニュアル配布、避難所開設演習 |
| 秋 | 地震、土砂災害、停電 | 防災週間訓練、備蓄品見直し、電源喪失訓練 |
| 冬 | 雪害、凍結事故、住宅火災 | 除雪計画、防火指導、暖房器具の安全講習 |
例えば、夏には「台風接近時の避難誘導訓練」や「ゲリラ豪雨を想定した水害マニュアルの再確認」などが行われます。
一方、冬には「住宅火災予防運動」や「雪道運転訓練」など、寒冷期特有のリスクに備える啓発活動が重視されます。
企業においては、こうした季節変動を踏まえて、事業継続計画(BCP)の見直しや従業員向けの訓練、設備・備品の点検強化などを年次スケジュールに組み込んで対応しています。
特にライフライン系・物流系企業では、災害による供給停止を最小限に抑えるため、平時から綿密な計画が求められます。
ただし、課題としては「防災活動の属人化」や「形骸化」などが挙げられます。
担当者が変わるごとに活動の継続性が損なわれるケースもあるため、社内・庁内マニュアルの標準化や教育体制の整備が不可欠です。
FAQ
Q:季節によって本当に災害ってそんなに違うんですか?
A:はい。たとえば夏は台風、冬は火災や凍結事故が多く、行政や企業はその季節に応じた準備をしています。
出典リスト
防災イベントやキャンペーン情報も要チェック

のいぼうラボ イメージ
「防災イベントやキャンペーン情報も要チェック」と感じる人は多く、防災を身近に学ぶ機会としてイベント活用を検討している方にとって有益な情報です。
毎年9月を中心に、行政・企業・市民団体が多彩な啓発活動を実施しています。
要点まとめ
9月は全国的に防災関連イベントが集中
官公庁・自治体・企業・NPOなどが連携して実施
無料で参加できる訓練・展示・セミナーが多数
オンラインイベントも年々充実
実践的な学びや防災グッズ配布など参加メリットが多い
防災に関するイベントやキャンペーンは、防災知識を楽しみながら学べる貴重な機会です。
特に毎年9月の「防災週間」を中心に、全国各地で数多く開催されています。
こうしたイベントの目的は、「備えの大切さを体験ベースで広めること」です。
たとえば、2025年には新潟県で開催予定の「ぼうさいこくたい(防災推進国民大会)」では、最新の防災技術や取組みを紹介する展示やワークショップ、防災体験プログラムなどが予定されています(出典:ぼうさいこくたい2025)。
一方、首都圏や地方自治体でも、独自の防災キャンペーンが充実しています。
たとえば、東京都では以下のような例があります:
帰宅困難者訓練(新宿駅・渋谷駅周辺で実施)
親子向け「防災ひろば」イベント(防災教育を体験形式で実施)
マンション管理組合向け防災セミナー
また、企業も積極的にキャンペーンを展開しており、イオン・東急ハンズ・無印良品などが防災用品の体験会や特設コーナーの設置、SNS投稿キャンペーンなどを実施しています。
たとえば「非常持ち出し袋の中身を見直すワークショップ」や「防災クイズに答えてグッズをもらえる企画」など、参加型の工夫が目立ちます。
さらに、近年はオンライン化されたイベントも拡充しており、YouTubeライブ配信やZoomセミナー、SNS投稿参加型企画など、家庭から気軽に参加できる形へと進化しています。
企業や自治体の公式サイト、または「ぼうさいこくたい」などの総合ポータルを活用することで、直近のイベント情報を簡単にチェックできます。
注意点としては、「一過性の参加」で終わってしまいがちな点です。
イベント参加後は、防災グッズの見直しや家族での避難経路確認など、実際の行動に結びつけることが重要です。
FAQ
Q:防災イベントって子どもでも参加できますか?
A:はい、多くのイベントでは子ども向けの体験コーナーやクイズラリーなどが用意されています。家族で楽しみながら防災を学べるのでおすすめです。
出典リスト
9月はなぜ「防災の月」なのか?のポイント!
記事のポイント まとめです
9月1日は防災の日として1959年に制定された
1923年9月1日の関東大震災が制定のきっかけである
毎年8月30日〜9月5日は防災週間として定められている
台風の多い時期と重なり、防災訓練に適している
防災とは災害の被害を未然に防ぎ、最小化する行動全般を指す
防災には予防・応急・復旧の3段階がある
防災は国や自治体、企業、個人が連携して取り組むべき課題である
防災週間中は全国で訓練や啓発イベントが集中的に行われる
関東大震災の経験から複合災害への備えの重要性が認識された
訓練が形骸化しないよう、現実的な内容にする必要がある
9月は企業のBCP訓練や安否確認システムの点検も盛んに行われる
防災教育は学校現場や地域社会でも積極的に導入されている
家庭での備えや行動の見直しが重要な時期である
防災の日は9月以外にも設定されており、通年で意識を高める必要がある
防災訓練は災害が起こる前に行うことで最大の効果を発揮する
【参考情報】
内閣府 防災情報のページ
https://www.bousai.go.jp/首相官邸 防災の手引き
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/総務省消防庁 防災eカレッジ
https://www.fdma.go.jp/relocation/bousai-education/気象庁 関東大震災 概要ページ
https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/higai/1923kantou/東京都防災ポータル(訓練・対策・イベント)
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/政府広報オンライン 防災の日/防災週間関連
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202308/2.html国連 国際防災の日(UNDRR)
https://www.undrr.org/津波防災の日 特設ページ(日本政府)
https://www.data.jma.go.jp/tsunami/tsunami_info.htmlPR TIMES 防災月間に関する民間企業の取り組み事例
https://prtimes.jp/
/関連記事 日本では地震や台風などの災害が頻繁に発生するにもかかわらず、防災意識が十分に浸透しているとは言えません。防災意識 低い 理由として、正常性バイアスの影響や防災教育の不足、日常の忙しさなどが挙げられます ... 続きを見る 防災グッズ選びに何を揃えればいいか迷っていませんか?この記事では「わかりやすい 防災用品 チェックリスト」を基に、日常からできる備え方と基本知識を解説します。 まず、「防災とは何ですか? ... 続きを見る 「防災 クイズ 大人向け」で検索しているあなたは、災害に備えた知識を楽しみながら身につけたいと感じていませんか? いざという時に役立つ行動力や判断力を、日常の中で無理なく養う方法。それが ... 続きを見る 災害が多い日本で、「小学生にも防災の大切さを伝えたい」と考える保護者や教育関係者の方も多いのではないでしょうか。 そんなときにおすすめなのが、防災クイズ小学生向けの教材です。 この記事で ... 続きを見る

関連記事なぜ防災意識は低いのか?日本の現状と意識向上の必要性

関連記事初心者でも安心!わかりやすい防災用品チェックリスト活用法

関連記事大人向けの防災クイズを習慣化!日常に備えを取り入れる新常識

関連記事防災クイズ小学生向け30問|親子で楽しく学べる防災対策集
