「セコムに加入していたのに空き巣に入られた…」この事実は、何よりも大きな衝撃と不安をもたらします。
そもそもセコムって何ですか、という根本的な疑問や、そもそも空き巣って何ですか、という初歩的な問いさえ頭に浮かぶかもしれません。
見逃したかもしれない空き巣が入る前兆とは何か、そして今後は空き巣に入られやすい家の特徴と対策をどうすれば良いのか。
また、セコムは狙われやすい、あるいは逆効果という噂は本当なのか、強盗には意味ないのでは、という不安。
一方で、セコムで助かった事例も耳にします。
空き巣に入られたかも…警察を呼ぶ前に何をすべきか、そして被害に遭った後、警察はどう対応しますか?
その被害後の流れの中で、セコムの緊急対処と室内への進入方法はどのように行われ、被害に遭った場合のセコムの保証内容は一体どうなっているのでしょうか。
この記事では、これら全ての疑問に答えるため、まとめとしてセコムで空き巣に入られた時の対策を、公的な情報に基づき専門的かつ具体的に解説します。
記事のポイント
- 被害に遭った直後に取るべき具体的な行動がわかる
- なぜセキュリティシステムがあっても侵入されるのか、その原因を理解できる
- セコムの補償制度や、今後のための物理的な防犯対策がわかる
- 被害後の精神的・法的な支援に関する公的窓口を知ることができる
セコム契約中に空き巣に入られた直後の対応

のいぼうラボ イメージ
この章では、セコム契約中に空き巣被害に遭った場合の初動対応を解説します。
安全の確保、警察への連絡、そしてセコムの保証請求までの具体的な流れを詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
ポイント
- 空き巣に入られたかも…警察を呼ぶ前に
- 警察はどう対応しますか?被害後の流れ
- 被害に遭った場合のセコムの保証内容
空き巣に入られたかも…警察を呼ぶ前に

のいぼうラボ イメージ
帰宅した際に玄関の鍵が開いている、窓ガラスが割れている、あるいはドアノブ周辺に見慣れない傷があるなど、ご自宅の様子に普段と違う異変を感じた場合、それは空き巣被害のサインかもしれません。
このような状況に直面すると、強い不安から「すぐに中を確認したい」という気持ちに駆られるのは自然なことです。
しかし、その 本能的 な行動は、時として大変な危険を伴います。
犯人がまだ室内に潜んでいる可能性もゼロではないため、何よりもまずご自身の安全を最優先に確保することが大切になります。
もし「空き巣に入られたかもしれない」と直感したら、決して家の中には入らず、すぐにその場を離れてください。
たとえ貴重品が気になったとしても、あなたとご家族の安全に勝るものはありません。
鉢合わせになった犯人がパニックに陥り、居直り強盗などに豹変する不測の事態も考えられます。
まずは隣人の家や、人通りのある近くのコンビニエンスストアなど、第三者の目がある安全な場所まで速やかに移動しましょう。
携帯電話などで外部と連絡が取れる場所に身を置くことが、冷静な判断を下すための第一歩です。
安全な場所に移動したら、110番に通報する前に、一度深呼吸をして落ち着くことが重要です。
ただ、これはご自身の目で室内を確認しに行くという意味ではありません。
むしろ、その逆です。
室内への立ち入りは、犯人と遭遇するリスクを高めるだけでなく、犯人が残した指紋、足跡、髪の毛といった重要な証拠を意図せず乱してしまう恐れがあります。
警察官が到着するまで、ご自宅は「犯罪現場」であるという認識を持つことが求められます。
安全が完全に確認できる場所から、落ち着いて警察へ連絡し、その後の指示を仰ぐようにしてください。
もし可能であれば、ご自身の安全を確保した上で、自宅から少し離れた場所から不審な人物や車両が立ち去らないかを確認することも、後の捜査に役立つ場合があります。
警察はどう対応しますか?被害後の流れ

のいぼうラボ イメージ
110番通報を受けて警察官が到着すると、まず人命の安全確保が最優先されます。
犯人が室内に残っていないか、負傷者はいないかを確認し、現場周辺を立ち入り禁止にするなどして安全な状況を確保します。
これが完了して初めて、本格的な捜査が開始されるという流れです。
現場検証
警察官は、犯人が残した指紋や足跡、その他の遺留品といった証拠を収集するため、詳細な現場検証を実施します。
多くの場合、制服の警察官だけでなく、専門の鑑識課員が派遣され、科学的な手法で証拠を収集します。
指紋や足跡はもちろん、犯人が残したかもしれない髪の毛一本、衣服の繊維、こじ開けられた窓枠の工具痕など、あらゆるものが犯人特定に繋がる重要な証拠となり得ます。
このため、警察官が到着するまで現場の物を動かしたり、片付けたりしないように、という指示は厳守する必要があります。
あなたの協力が、捜査の進展に大きく影響します。
この検証には数時間を要することもあり、その間、被害者は別の場所で事情聴取を受けるなど、待機を求められるのが一般的です。
被害届の提出
現場検証と並行して、または終了後、被害者から被害の状況について詳細な聞き取りが行われます。
何を、どれくらい盗まれたのか、発見時の状況はどうだったかなどをできる限り具体的に説明し、正式な「被害届」を提出することになります。
この聞き取りをスムーズに進めるため、可能であれば、盗まれたと思われる品物のリストをあらかじめ作成しておくと良いでしょう。
特に、家電製品の型番やシリアルナンバー、宝飾品の写真、購入時の保証書などがあれば、被害品の特定に大いに役立ちます。
警察官はあなたの供述に基づいて「被害届」の書類を作成し、最後にあなたが内容を確認して署名・捺印をします。
この被害届は、後の保険金請求手続きなどでも必ず必要となる公的な書類ですので、正確な情報を提供することが求められます。
手続きの際には、保険会社などから提出を求められる「被害届受理番号」を忘れずに控えておくことが肝心です。
その後の捜査と情報提供
被害届が受理されると、警察は収集した証拠や聞き取り内容を基に本格的な捜査を開始します。
しかし、すぐに犯人が見つかるとは限りません。
捜査の進捗について気になる点があれば、担当の警察署に問い合わせることも可能です。
もし犯人が検挙され、盗まれた品物が発見された場合は、所定の手続きを経て返還されることになります。
また、被害に遭った精神的ショックは計り知れないものがあります。
警察では、専門の相談員によるカウンセリングを受けられる窓口を設けているほか、必要に応じて、各都道府県にある「犯罪被害者支援センター」のような公的な外部機関を紹介してくれることもあります。
一人で抱え込まず、こうした支援制度を活用することも検討してください。
被害に遭った場合のセコムの保証内容
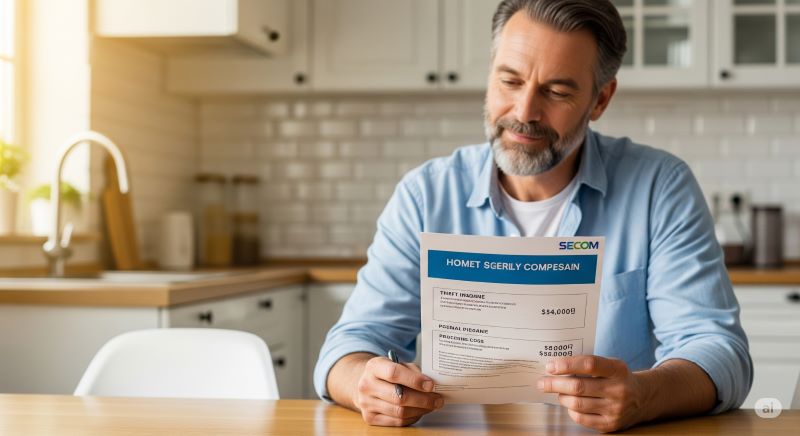
のいぼうラボ イメージ
セコムのホームセキュリティ契約には、万が一の侵入被害に備えた補償制度が付帯しているのが一般的です。
これは、盗まれた品物の金銭的価値だけでなく、破壊された鍵の交換や窓ガラスの修理といった、被害直後に発生する予期せぬ出費に対する経済的打撃を緩和するための、重要なセーフティネットと言えます。
ここで理解しておきたいのは、この補償制度はあくまでセキュリティサービスに付帯する機能の一つであり、ご自身で別途契約する火災保険などの「損害保険契約」とは異なる性質を持つという点です。
セコムが提供する補償は、被害に対する初期的なカバーを目的としたものであり、全ての損害を補填するものではない可能性があります。
そのため、まずはご自身の契約書や約款を確認し、どのような補償が受けられるのかを正確に把握することが不可欠です。
以下に示すのは、あくまで標準的な契約における一例となります。
| 補償の種類 | 対象となる損害 | 補償上限額(一例) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 盗難保険 | 現金、貴金属、美術品などの盗難 | 最大50万円 | 1回の事故につき5,000円の自己負担額(免責金額)が設定されている場合があります。 |
| 盗難保険 | 上記以外の家財(パソコン、バッグ等)の盗難 | 最大200万円 | |
| 建物損害修復費用見舞金 | 侵入時に破壊された窓ガラスやドア錠などの修復費用 | 最大100万円 | 損害額が10万円未満の場合は対象外となるなど、支払いには条件があります。 |
※2025年7月時点での一例です。
セコム公式サイト 充実の補償や付帯サービスを基に作成。
正確な情報はご自身の契約内容をご確認ください。
補償を申請する際の流れと注意点
実際にこの補償制度を利用するには、いくつかの手続きと注意点があります。
まず、申請プロセスの第一歩として、前述の通り、警察から「被害届受理番号」を取得することが必須です。
この番号がなければ、保険金の請求手続きに進むことができません。
受理番号を得た上でセコムに連絡し、所定の保険金請求書を取り寄せることになります。
その際、被害状況を証明するために、損害箇所の写真や、盗まれた品の購入時のレシート、修理費用の見積書など、関連書類をできるだけ多く準備しておくと、その後の手続きが円滑に進みます。
次に、補償の対象範囲について注意が必要です。
例えば、自己負担額(免責金額)が5,000円に設定されている場合、被害総額から5,000円を差し引いた金額が支払われることになります。
また、建物損害修復費用見舞金は、あくまで「見舞金」という位置づけであり、実際の修理費全額が支払われるわけではない点も理解しておく必要があります。
損害額に一定の基準(例:10万円以上)が設けられていることが多く、軽微な損害では対象外となる可能性があります。
さらに、特に注意したいのが、宝飾品や美術品といった高価な物品の扱いです。
日本損害保険協会 損害保険Q&Aによると、1個または1組の価額が30万円を超えるような高価品は「明記物件」として扱われます。
これらは、事前に保険契約上でその存在を申告していない限り、万が一盗難に遭っても補償額に上限が設けられたり、場合によっては補償の対象外となったりすることがあります。
最後に、契約者の故意または「重大な過失」によって生じた損害は、補償されないのが一般的です。
例えば、長期間にわたって窓の鍵を開けっ放しで家を空けていた、といったケースがこれに該当する可能性も否定できません。
何が「重大な過失」にあたるかは個別の状況によって判断されるため、一概には言えませんが、日頃から基本的な防犯意識を持つことが、万が一の際に自身を守ることにも繋がります。
補償利用時の注意点
この補償制度を利用する際には、いくつか注意点があります。
まず、警察から「被害届受理番号」を取得しておく必要があります。
これは保険金請求の際に必須となるからです。
また、一般的な損害保険のルールとして、1個または1組の価額が30万円を超えるような高価な貴金属や美術品は「明記物件」と呼ばれ、事前に申告がないと全額補償の対象外となることがあります。
日本損害保険協会 損害保険Q&Aによると、このような高価品は別途保険契約で明記する必要があるとされています。
最後に、契約者の故意または「重大な過失」によって生じた損害は、補償の対象外となるのが一般的です。
長期間にわたって施錠せずに家を放置していた、といったケースがこれに該当する可能性も否定できません。
なぜセコムの家が空き巣に入られたのか

のいぼうラボ イメージ
この章では、なぜセコムの家が空き巣に入られたのか、その原因と背景を解説します。
空き巣の手口や家の弱点、そして今後の具体的な防犯対策までを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
ポイント
- そもそも空き巣って何ですか?
- そもそもセコムって何ですか?
- 空き巣に入られやすい家の特徴と対策
- 見逃した?空き巣が入る前兆とは
- セコムの緊急対処と室内への進入方法
- セコムは狙われやすい?逆効果という噂
- 強盗には意味ない?セコムで助かった事例
- まとめ:セコムで空き巣に入られた時の対策
そもそも空き巣って何ですか?

のいぼうラボ イメージ
「空き巣」とは、一般的に家主や住人が不在の住宅に侵入し、金品を盗む犯罪行為、またはその犯人を指す言葉です。
これは法律上の正式な用語ではなく、刑法では「侵入窃盗」という犯罪類型の一つの手口として分類されます。
単に留守宅を狙う行為を指す、社会的に広く認知された呼称と理解すると良いでしょう。
彼らが狙う「金品」は、現金や貴金属だけに限りません。換金が容易なノートパソコンやタブレット、ゲーム機、あるいは高級腕時計やブランド品のバッグなども主要なターゲットとなります。
さらに危険なのは、通帳や印鑑、キャッシュカード、パスポートといった個人情報に関わる重要書類を盗み出し、不正利用やさらなる犯罪に悪用するケースもあることです。
その侵入の手口は年々巧妙化していますが、同時に非常に単純な方法も依然として多用されています。
ピッキングやサムターン回しといった特殊な技術で鍵を開ける手口に加え、ドライバーなどでドアや窓をこじ開ける、あるいは単純にガラスを破壊するといった物理的な手口も後を絶ちません。
しかし、最も注意すべきは、鍵のかかっていない玄関や窓から堂々と侵入する「無施錠」による被害が、依然として侵入窃盗全体の半数近くを占めているという事実です。
前述の通り、侵入窃盗にはこの「空き巣」の他にも、夜間に家人が就寝している隙を狙って侵入する「忍込み」や、日中に家人が在宅しているものの、昼寝や他の部屋での作業中に気づかれないよう音を立てずに侵入する「居空き」といった手口があります。
これらは家人と鉢合わせする危険性が非常に高く、単なる窃盗から居直り強盗へと発展する可能性もはらんでいます。
法律上、この行為は住居侵入罪と窃盗罪という二つの犯罪が結合した、極めて悪質なものと位置づけられています。
発覚すれば当然ながら逮捕され、厳しい刑事罰が科されることになります。
警察庁 住まいる防犯110番の統計によれば、住宅を対象とした侵入窃盗の中で、この「空き巣」が占める割合は依然として最も高く、住宅防犯を考える上で避けては通れない中心的な脅威となっています。
単に財産を失うという物理的な損害だけでなく、自宅という最も安全であるべきプライベートな空間を侵されることによる精神的な被害も極めて大きい、深刻な犯罪なのです。
そもそもセコムって何ですか?

のいぼうラボ イメージ
セコムとは、1962年に日本警備保障株式会社として創業し、日本で初めてオンライン・セキュリティシステムを事業化した、警備サービス業界のリーディングカンパニーです。
現在では一般的に「セコム」という言葉が、同社が提供するホームセキュリティサービスそのものを指して使われることも多くなっています。
ちなみに、今では当たり前に使われている「ホームセキュリティ」という言葉自体、1981年にセコムが家庭向けのサービスを発売した際に作られた造語です。
その中核となるサービスは、住宅に設置した各種センサーが24時間365日体制で異常を監視し、侵入や火災などを検知すると、コントロールセンターに自動で通報される仕組みです。
そして、全国に約2,600ヶ所(2025年7月時点。出典:セコム公式サイト)ある緊急発進拠点から、専門の訓練を受けた緊急対処員が現場へ駆けつけるというものです。
この監視システムを支えているのが、目的に応じて設置される多様なセンサーです。
例えば、窓やドアの開閉を検知する「マグネットセンサー」、室内の人の動きや熱を捉える「空間センサー(赤外線センサー)」、ガラスが割れた際の特有の音や振動を検知する「ガラス破壊センサー」などが侵入対策に用いられます。
これらに加え、火災の煙を検知する「火災センサー」や、ボタン一つで通報できる「非常ボタン」も標準装備されているのが一般的で、防犯以外の脅威にも対応しています。
また、異常信号を受け取るコントロールセンターも、単なる自動応答システムではありません。
専門のスタッフが24時間体制で常駐し、異常信号の種類によっては、まず契約者に電話連絡を入れて誤作動でないかを確認するなど、状況に応じた的確な判断を下します。
そして、出動指令を受けて現場に向かう緊急対処員も、厳しい訓練を受けたプロフェッショナルです。
初期消火や救命救急、さらには犯人と遭遇した場合の適切な対応方法など、様々なスキルを身につけており、ただ現場に到着するだけではない質の高い対応が期待されます。
言ってしまえば、セコムは単なる警報装置ではなく、最新の「テクノロジー(検知)」、専門的なスキルを持つ「人(通報・駆けつけ)」、そして被害発生時の「制度(補償)」までを含む、包括的な安全・安心のサービス・エコシステムであると考えられます。
空き巣に入られやすい家の特徴と対策

のいぼうラボ イメージ
侵入窃盗犯は、闇雲にターゲットを選んでいるわけではありません。
彼らは犯行前に必ず下見を行い、「リスクが低く、リターンが高い」と判断した家を狙う傾向があります。
言い換えれば、侵入が容易で、人目につきにくく、かつ発覚しにくい家が標的とされるのです。
警察庁の防犯情報などを参考にすると、いくつかの共通した特徴が浮かび上がります。
狙われやすい家の特徴
まず、物理的に「死角が多い家」は非常に危険です。
高い塀や手入れされていない生い茂った庭木は、道路からの視線を遮り、犯人が玄関や窓で作業する姿を隠す格好の場所を提供してしまいます。
エアコンの室外機や物置なども、身を隠したり、2階へよじ登るための足場として利用されたりする恐れがあります。
次に、「留守だと分かりやすい家」も標的になりがちです。
ポストに郵便物や新聞が溜まっている、夜になっても洗濯物が干したままになっている、毎日きっかり同じ時間に室内灯が消えるなど、生活パターンが外部から容易に読み取れる家は、不在のタイミングを特定されやすくなります。
最近では、SNSで旅行や長期の外出を知らせる投稿も、留守を公言しているようなものなので注意が必要です。
また、「窓やドアの守りが弱い家」は、侵入犯にとって格好のターゲットです。
例えば、窓の鍵が簡素なクレセント錠(窓の半月状の鍵)しかない、玄関が旧式の刻みキーである、勝手口のドアが簡易的なものになっているなど、物理的に破壊したり、こじ開けたりするのに時間がかからないと判断されると、侵入を試みられる可能性が高まります。
最後に、建物だけでなく「地域住民の関心が薄い地域」という環境要因も無視できません。
隣近所の付き合いが希薄で、住民がお互いに無関心な地域では、見知らぬ人物がうろついていても怪しまれにくいものです。
街灯が少なく夜間に暗い場所が多い、住民の入れ替わりが激しいアパートが多いといった環境も、犯人にとっては活動しやすい条件が揃っていると言えるでしょう。
今すぐできる対策
これらの特徴の逆を実践することが、有効な防犯対策の第一歩となります。
まず基本となるのは、日々の習慣です。短時間の外出であっても、玄関や勝手口はもちろん、浴室やトイレといった小さな窓に至るまで、全てのドアと窓の鍵をかける習慣を徹底することが最も重要です。
また、家の周りを常に整理整頓し、脚立やゴミ箱など、侵入の足場になりそうなものを放置しないように心がけましょう。
環境面では、家の見通しを良くすることが大切です。
庭木を定期的に剪定して死角をなくし、人の動きを感知して点灯するセンサーライトを玄関や裏口、駐車場などに設置するのが効果的です。
侵入犯は「光」と「音」を嫌うため、家の周りに防犯砂利を敷き、歩くと大きな音が出るようにするのも良いでしょう。
さらに、留守を悟られない工夫も有効です。長期で家を空ける際は、新聞や郵便物の配達を一時的に止める手続きをします。
タイマー付きの照明やラジオを活用し、在宅しているかのように見せかけることも侵入をためらわせる一因となります。
そして、最終的には地域全体で防犯意識を高めることが、何よりの対策となります。
日頃から近所付き合いを大切にし、お互いに挨拶を交わすだけでも、不審者が入り込みにくい雰囲気が醸成されます。
地域の防犯活動に参加するなど、「地域の目」で街全体を守るという意識を持つことが、あなた自身の家の安全にも繋がるのです。
見逃した?空き巣が入る前兆とは

のいぼうラボ イメージ
空き巣犯は、犯行に及ぶ前にターゲットの家を入念に下見し、住人の生活パターンや家族構成、資産状況などを探ることがあります。
彼らは、どの時間帯が留守になるのか、家に犬はいるのか、警備システムの有無、そしていざという時の逃走経路は確保できるか、といった情報を集め、リスクを最小限に抑えようとします。
その過程で、彼ら特有のサインである「マーキング」を残していくことがあると言われています。
マーキングとは、玄関の表札やインターホン、郵便受け、ガスメーターなど、目立ちにくい場所に、住人の情報を暗号化して記す小さな目印のことです。
これは、小さなシールであったり、油性ペンで書かれた記号や文字であったり、カッターナイフでつけられた僅かな傷であったりと、様々な形態が報告されています。
例えば、「M(男)W(女)S(一人暮らし)R(留守)」といったアルファベットや数字、シールの色などで情報を仲間内で共有するとされています。
もちろん、全ての空き巣犯がマーキングを行うわけではありませんし、子供のいたずらや水道業者などの正規の目印である可能性も考えられます。
見慣れないシールが全てマーキングであると過度に恐れる必要はありません。
しかし、もし自宅の玄関周りなどに不審なシールや落書きを見つけた場合は、単に放置するのではなく、まずスマートフォンなどでその状況を写真に撮って記録しておきましょう。
その後、速やかにそれを取り除き、念のため最寄りの警察署や交番に「このような不審な印があった」と情報提供することも、地域の防犯に繋がります。
また、マーキング以外にも注意すべき前兆は存在します。
例えば、見知らぬ人物が家の周りを頻繁にうろついている、理由の不明な無言電話や、押してすぐに立ち去るインターホンが増えた、といった現象も下見の可能性があります。
無言電話は在宅状況を確認する常套手段です。
さらに、郵便受けに不自然にチラシが挟まっていたり、ドアの隙間に小さな石が置かれていたりすることもあります。
これらは、住人がそれに気づき、取り除くかどうかで、その家の防犯意識や在宅状況を測るためのテストである可能性が指摘されています。
こうした些細な、しかし普段とは違う変化に気づくことが、被害を未然に防ぐための重要な一歩となるかもしれません。
日頃から自宅の周辺環境に注意を払う意識が大切です。
セコムの緊急対処と室内への進入方法

のいぼうラボ イメージ
セコムのホームセキュリティが異常を検知した際、どのようなプロセスで対処が行われるのかを具体的に理解しておくことは大切です。
これは、セキュリティシステムの真の価値を正しく評価する上で重要なポイントとなります。
この一連の流れは、単なる速さだけでなく、誤報を減らすための正確さとのバランスを考慮して設計されています。
異常検知から出動まで
まず、窓やドアに設置された開閉センサーや、室内の人の動きを捉える空間センサーなどが異常を検知します。
その信号は、暗号化された通信網を通じて、即座にセコムのコントロールセンターへ送信されます。
コントロールセンターでは、専門の管制員が24時間365日体制で常駐しており、どのセンサーが、どのような順番で反応したかといった情報を分析します。
例えば、窓のセンサーと直後の廊下の空間センサーが連続して反応した場合、侵入の可能性が非常に高いと判断します。
状況によっては、出動指示を出す前に、まず契約者の携帯電話などに連絡を入れ、誤作動でないかを確認するステップを踏みます。
これは、ご家族が帰宅時にセット解除を忘れた、といった単純なミスによる不要な出動を避けるためです。
この確認の電話で応答がない、あるいは事前に定めた「暗証の言葉」が異なる場合は、異常事態と判断し、即座に次のステップへ移行します。
出動指示が出されると、GPSなどを活用した高度な指令システムにより、現場に最も近い緊急発進拠点に待機する、最も早く到着できる緊急対処員が自動的に選ばれて現場へ急行します。
現場での対応と進入
現場に到着した緊急対処員は、まずサイレンを鳴らさずに静かに接近し、建物の外周を慎重に確認します。
窓ガラスが割られていないか、ドアがこじ開けられた痕跡はないかなど、異常の有無を目視でチェックします。
ここで、契約時に預かっている鍵の存在が重要になります。
この鍵は厳重に管理されており、正規の出動指令がなければ持ち出すことはできません。
外周の確認で明らかに侵入の痕跡がある場合や、コントロールセンターを通じた契約者からの許可がある場合など、所定の条件を満たした場合に限り、対処員はこの預かりキーを使用して玄関から室内へ入り、状況の確認を行います。
室内に入った対処員の役割は、まず第一に状況を正確に把握し、身の安全を確保しながら、室内に不審者がいないか、被害の状況はどうなっているかを確認することです。
彼らは犯人と格闘するのではなく、現場の情報を的確にコントロールセンターへ報告し、警察との連携を密に取るための「目」と「耳」として機能します。もし負傷者がいれば、応急手当を行うなどの訓練も受けています。
このように、セコムの対処員は、ただ現場に行くだけでなく、契約者の財産と安全を守るため、定められた手順に則って室内確認まで行うのが基本です。
この「プロが物理的に現場を保全し、警察と連携する」という点が、警報音を鳴らすだけの自己防衛グッズとの本質的な違いと言えるでしょう。
セコムは狙われやすい?逆効果という噂

のいぼうラボ イメージ
「セコムのステッカーが貼ってある家は、お金持ちだと思われてかえって狙われやすいのでは?」という、いわゆる「逆効果」説を耳にすることがあります。
これは、ホームセキュリティの導入を検討する、あるいは利用している多くの人が一度は考える疑問かもしれません。
セキュリティの象徴が、逆に危険を呼び込むのではないかという不安です。
この説に対する明確な公的データはありませんが、複数の視点からその是非を考えることができます。
まず、大多数の専門家が支持するのは、ステッカーが「強力な抑止力として機能する」という見方です。
侵入窃盗犯の多くは、犯行が発覚するリスクを極度に嫌い、短時間で目的を遂げることを望みます。
警察庁の調査では、侵入を諦める理由として「声をかけられた」「防犯カメラやセンサーがあった」などが上位に挙げられており、犯人が人目や防犯システムを強く意識していることがわかります。
セコムのステッカーは、まさに「この家は監視されており、異常があれば数分でプロが駆けつける」という明確な警告です。
この心理的なプレッシャーは、一般的な空き巣犯にとっては犯行をためらわせるのに十分な効果を持つと考えられます。
ただ、逆の視点に立てば、この説が全く根拠のないものとも言い切れません。
非常に計画的で大胆な窃盗団など、特定のスキルや情報網を持つ特殊な犯罪者にとっては、話が別になる可能性があります。
彼らにとっては、一般的な家ではなく、より価値のある資産が眠る家を狙う方が効率的です。
その際、セコムのステッカーが「それなりの防犯対策を乗り越えてでも侵入する価値のある資産がある家」という選別のための目印として、逆機能してしまう可能性もゼロとは断言できません。
しかし、そもそもこの議論は、ステッカー単体の効果に焦点を当てすぎている側面があります。
ステッカーの真価は、それが示す「背景」にあります。つまり、センサーネットワーク、24時間体制の監視センター、そして迅速に駆けつける緊急対処員という、目に見えない包括的な防衛システムが背後にあるという事実です。
ステッカーは、そのシステムの存在を外部に告知する、いわば氷山の一角に過ぎません。
結局のところ、ステッカーが抑止力として働くか、逆効果となるかは、対峙する犯人のタイプやその時の状況に左右される不確定な要素です。
しかし、統計的に大多数を占める日和見的・機会的な空き巣犯に対する圧倒的な防犯効果を考えれば、プロの窃盗団に狙われるという稀なリスクよりも、抑止力としてのメリットの方がはるかに大きいと考えるのが妥当でしょう。
重要なのは、ステッカーだけに頼るのではなく、日々の施錠習慣や物理的な防犯対策と組み合わせ、システム全体で家を守るという意識です。
強盗には意味ない?セコムで助かった事例

のいぼうラボ イメージ
「在宅中に襲ってくるような凶悪な強盗相手では、セコムも意味がないのでは?」という声も聞かれます。
この疑問の根底には、留守宅を狙う「空き巣(侵入窃盗)」と、家人に暴力や脅迫を加えて金品を奪う「強盗」との、犯罪性質の明確な違いがあります。
確かに、侵入と同時に家人を拘束するような計画的で凶悪な強盗に対して、ドアや窓のセンサーによる自動検知が間に合わない、あるいは無力化されてしまうケースは想定されます。
しかし、この点を以て「意味がない」と結論づけるのは早計です。
セコムのホームセキュリティは、こうした在宅中の緊急事態を想定した、重要な機能を備えています。
それが、身の危険を感じた時に手動で通報できる「非常ボタン」の存在です。
この非常ボタンは、コントロールパネルだけでなく、寝室やリビングなど、すぐに手の届く場所に別途設置したり、携帯型のリモコンとして身につけておいたりすることも可能です。
就寝中に不審な物音で目覚めた時や、玄関先で不審者に押し入られそうになった瞬間にこのボタンを押すことで、センサーの検知を待つことなく、コントロールセンターに最高レベルの緊急事態を通報できます。
この信号は、単なる侵入検知とは異なり、人の生命に危険が及んでいる可能性を示すものであるため、即座に警察への通報と緊急対処員の派遣が手配されます。
実際、過去の報道やセコムが公開する事例の中には、この非常ボタンによって強盗被害から助かった、あるいは犯人が何も盗らずに逃走し、被害を最小限に食い止められたというケースも報告されています。
警備会社の迅速な駆けつけは、犯人にとって計画が破綻したことを意味し、犯行を断念させる強いプレッシャーとなります。
また、当初は空き巣目的で侵入した犯人が、予期せず家人と鉢合わせしてしまい、パニックから「居直り強盗」に豹変するというケースも少なくありません。
このような不測の事態においても、侵入の初期段階でセンサーが異常を検知していれば、すでに警備員が駆けつけている最中かもしれません。たとえセンサー検知が無くとも、非常ボタンを押すことで助けを呼べるという事実は、被害者のパニックを抑え、冷静な対処を促すための大きな心理的な支えとなり得ます。
到着した対処員は、犯人への対応だけでなく、負傷者の応急手当や警察への状況説明など、混乱した現場での様々なサポートを行います。
したがって、強盗に対して100%の防御を保証するものではありませんが、複数の防御ラインを持つことで被害の発生確率を下げ、万が一の際には被害を極小化し、身の安全を確保する上で重要な役割を果たすと考えられます。
まとめ:セコムで空き巣に入られた時の対策
記事のポイント まとめです
- 帰宅時の異変に気づいたら、まず身の安全を確保し、家には入らない
- 安全な場所から速やかに110番通報し、警察の到着を待つ
- 警察が到着するまで、現場の証拠を保全するため室内の物には触れない
- 警察への通報後、セコムの契約者専用窓口にも連絡を入れる
- 警察の現場検証に協力し、被害品の詳細をまとめて正確な被害届を提出する
- セコムの補償制度を利用するため、被害届受理番号を警察から取得する
- ご自身の契約プランにおける盗難保険や見舞金の内容を約款で確認する
- 加入している火災保険に盗難補償が付帯していないかも併せて確認する
- 空き巣の半数近くは無施錠が原因であり、日々の施錠習慣が最も重要
- 高い塀や生い茂った庭木など、家の死角を減らす対策を検討する
- ピッキングに強いCPマーク認定錠や補助錠で物理的な防御力を高める
- セコムのステッカーは、一般的な侵入犯への抑止力として機能すると考えられる
- 強盗など在宅時の危険には、非常ボタンの活用が有効な対策となる
- 被害後の精神的なケアのため、警察の相談窓口や犯罪被害者支援センターの利用を検討する
- 法的な手続きや損害賠償で不明な点があれば、法テラスなどの専門機関に相談する
参考情報一覧
- 警察庁(住まいる防犯110番): https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki26/
- 警視庁(侵入窃盗の被害にあわないために): https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/higai/akisu/akisu_jirei.html
- セコム公式サイト(ホームセキュリティ): https://www.secom.co.jp/homesecurity/
- セコム公式サイト(補償制度について): https://www.secom.co.jp/homesecurity/anshin/service.html
- ALSOK(侵入窃盗の傾向と防犯対策): https://www.alsok.co.jp/person/recommend/071/
- 日本損害保険協会(損害保険Q&A): https://www.sonpo.or.jp/
- 法テラス 公式サイト(犯罪被害者支援): https://www.houterasu.or.jp/higaishashien/
- 全国被害者支援ネットワーク: https://nnvs.org/
- SUUMOジャーナル(空き巣に狙われやすい家の特徴): https://suumo.jp/journal/2022/10/21/189333/
- 鍵のレスキュー(空き巣とは?手口や対策を解説): https://key-stations.jp/media/bouhan-knowledge/akisu/






