「大切な我が家が、もし空き巣被害に遭ってしまったら…」そう考えると、多くの方が不安になるのではないでしょうか。
「空き巣は捕まらない」という話を耳にすることもあり、その不安はさらに大きくなるかもしれません。
そもそも空き巣って何ですか、という基本的な疑問から、実際のところ空き巣の犯人が捕まる確率はどのくらいなのか、そして空き巣は何を盗むことが多いのかという具体例まで、気になる点は多いでしょう。
また、これらは危険と言われる空き巣に入られる前兆や、犯人が用いる空き巣がバレない手口、万が一の際の侵入されたかの確認法についても知っておきたいはずです。
知恵袋でのQ&Aで空き巣は捕まらない?という質問を見るたびに、空き巣で警察は動かないのではないか、実際の捜査の範囲とはどこまでなのか、犯人特定から空き巣が捕まるまでの流れはどうなっているのか、といった疑問は尽きません。
この記事では、そうした皆様の疑問に一つひとつお答えしていきます。
そして、空き巣捕まえ方の基本は事前の防犯対策であるという視点から、空き巣の被害に遭わないための具体的な方法を、専門的な情報に基づいて分かりやすく解説します。
この記事で理解が深まるポイント
記事のポイント
- 空き巣が捕まりにくいとされる統計的・構造的な理由
- 犯人が狙う家の特徴と巧妙な手口の具体例
- 警察の捜査の流れと限界、そして私たちができること
- 今日から実践できる具体的な防犯対策の数々
なぜ?空き巣が捕まらない理由と被害の実態

のいぼうラボ イメージ
この章では「空き巣とは何か」という基本から、実際の検挙率、犯行手口、狙われる家の前兆までを詳しく解説します。
空き巣被害のリアルな実態と、捕まりにくい根本的な理由がわかります。
ポイント
- そもそも空き巣って何ですか?
- 空き巣の犯人が捕まる確率はどのくらいか
- 空き巣は何を盗むことが多いのか具体例
- これらは危険!空き巣に入られる前兆
- 空き巣がバレない手口と侵入されたかの確認法
- 空き巣捕まえ方の基本は事前の防犯対策
そもそも空き巣って何ですか?

のいぼうラボ イメージ
はじめに、空き巣という言葉の正確な意味から確認していきましょう。
多くの方が耳にしたことのある言葉ですが、その定義や関連する犯罪の種類を深く理解することが、適切な防犯対策への第一歩となります。
空き巣とは、家人などが不在の住宅に侵入し、金品を盗む行為、またはその行為を行う犯人のことを指します。
この行為は、単一の犯罪ではなく、法的には二つの異なる犯罪が同時に成立することが一般的です。
一つは他人の財物を盗む「窃盗罪」、もう一つは正当な理由なく他人の住居に侵入する「住居侵入罪」です。
このため、空き巣犯はこれら二つの罪で裁かれることになり、社会に与える影響の大きさから見ても、決して軽視できない犯罪行為と言えます。
また、侵入窃盗には、侵入時の状況によって「居空き(いあき)」や「忍び込み(しのびこみ)」といった、よく似た言葉がありますが、これらは手口の悪質性や危険性が異なります。
空き巣
家人が学校や職場、買い物などで留守にしている昼間や、旅行などで長期間不在の間に侵入する、最も一般的な手口です。
居空き
家人が在宅中にもかかわらず、その注意が逸れている一瞬の隙を突く、非常に大胆な手口です。
例えば、庭の手入れに集中している間や、イヤホンで音楽を聴いている間、別の部屋で電話をしている間などが狙われます。
犯人は住人の存在を認識した上で犯行に及ぶため、鉢合わせのリスクも高く、万が一の際には強盗などに発展する危険性もはらんでいます。
忍び込み
家人が就寝している夜間に侵入する、最も悪質で精神的なダメージの大きい手口かもしれません。
プライベートな空間の最も深い部分まで侵される恐怖は、被害者に深刻なトラウマを残すことがあります。
物音を立てずに侵入し、目的を遂げるためには、高度な技術と慎重さが要求される犯行です。
このように、侵入窃盗は留守中だけでなく、私たちが自宅でくつろいでいる時間や寝ている時間でさえ発生しうる、非常に身近で危険な犯罪なのです。
これら三つの手口の中で「空き巣」の発生件数が最も多い背景には、犯人側のリスク計算があります。
住人が不在であるため、誰かに見られたり、通報されたりする危険性が格段に低くなります。
また、時間をかけて家の中を物色できるため、より多くの金品を盗み出すことが可能になります。
この記事では、こうした計画的かつ合理的な判断のもとで行われることが多く、侵入窃盗の中で大半を占める「空き巣」に焦点を当てて、その実態と有効な対策を詳しく掘り下げていきます。
空き巣の犯人が捕まる確率はどのくらいか

のいぼうラボ イメージ
「空き巣は捕まらない」という漠然としたイメージがありますが、実際の検挙率はどのようになっているのでしょうか。
この点は、防犯を考える上で非常に重要な指標となります。
結論から言うと、侵入窃盗の検挙率は他の犯罪と比較して決して高いとは言えず、約半数の犯人は捕まっていないのが現状です。
これは、単なるイメージではなく、警察庁が公表している公式な統計データによって裏付けられています。
その実態を、他の犯罪と比較しながら見ていきましょう。
| 犯罪手口 | 検挙率 |
|---|---|
| 侵入窃盗 | 52.4% |
| 非侵入窃盗(全体) | 45.8% |
| (内訳)万引き | 67.3% |
| (内訳)乗り物盗 | 8.4% |
参考資料:令和5年の刑法犯に関する統計資料
この表が示すように、2023年(令和5年)における侵入窃盗の検挙率は52.4%でした。
この数字は、発生した侵入窃盗事件のうち、およそ2件に1件は犯人が捕まっておらず、未解決のままになっていることを意味します。
さらに、この数値は前年の2022年(令和4年)の60.5%から8.1ポイントも低下しており、検挙がより一層難しくなっている厳しい現実を示唆しています。
なぜ空き巣の検挙は難しいのか
では、なぜ万引きの検挙率が7割近いのに対し、侵入窃盗の検挙はこれほど困難なのでしょうか。
その理由は、空き巣という犯罪が持つ特有の性質にあります。
一つは、犯行現場における証拠の乏しさです。
万引きは店舗という閉鎖された空間で行われ、店員や他の客、そして多数の防犯カメラによって犯行の瞬間が記録されやすい環境にあります。
一方、空き巣は家人が不在の状況を狙うため、直接的な目撃者が存在しません。
加えて、プロの犯人は手袋やマスクを着用して指紋や顔の特定を防ぎ、足跡を残さないよう最新の注意を払うため、犯人に直結する物証が極端に少ないのです。
もう一つの理由は、犯行の計画性の高さです。
多くの空き巣犯は、事前に侵入経路や逃走経路を入念に下見し、地域の地理や住民の生活パターンを把握した上で犯行に及びます。
また、レンタカーや盗難車を使用し、盗品もすぐに専門のルートで換金してしまうなど、犯行後の足取りを消すことにも長けています。
このような周到な準備が、警察の捜査をより一層困難にしているのです。
これらのデータと背景から導き出されるのは、被害に遭った後で犯人が捕まることを期待するよりも、いかに「被害に遭わないようにするか」という事前の対策が極めて大切である、という事実です。
検挙率の数字は、私たち一人ひとりが防犯意識を高めるべきであるという、社会への警鐘と捉えることができます。
空き巣は何を盗むことが多いのか具体例

のいぼうラボ イメージ
空き巣の犯人は、一体どのようなものを狙って侵入するのでしょうか。
犯人の行動は極めて合理的であり、そのターゲットは「リスクが低く、リターンが高い」ものに絞られます。
警視庁などの調査によると、被害品は換金しやすく、かつ短時間で持ち運びやすいものに集中する傾向が鮮明に見られます。
最も狙われるのは「現金」
被害品の中で、いつの時代も変わらず最も多いのは「現金」です。
犯人にとって現金が最も魅力的な理由は、その匿名性と即時性にあります。
足がつく心配がなく、盗んだ直後から使用できるため、わざわざ換金する手間やリスクを負う必要がありません。
多くの家庭である程度の現金を保管しているという想定のもと、犯人はタンスの引き出し、クローゼ-ット、仏壇、机の引き出しといった、人々が現金を隠しがちな場所を真っ先に探します。
現金以外に狙われやすい貴重品
現金以外では、犯人の「換金性」と「運搬性」という二つの基準を満たす、以下のようなものが盗難の対象となりやすいです。
貴金属・宝飾品
指輪、ネックレス、ピアス、腕時計といった貴金属や宝飾品は、その筆頭です。
小さく高価であるため、ポケットに入れて簡単に持ち運べるにもかかわらず、高値で取引されます。
犯人はこれらを専門の買取業者や闇市場で素早く換金します。
金やプラチナのような素材は、たとえ溶かされても価値が失われないため、特に狙われやすい傾向にあります。
キャッシュカード・クレジットカード
カード類そのものだけでなく、一緒に保管されていることの多い運転免許証などの身分証明書も同時に盗まれると、被害は深刻化します。
暗証番号を誕生日や電話番号など推測されやすいものに設定している場合や、カードと暗証番号のメモを一緒に保管している場合は、預金を引き出されたり、キャッシングされたりと、金銭的被害が瞬く間に拡大する極めて高いリスクをはらんでいます。
パソコン・タブレット
近年、物理的な価値だけでなく、内部に保存された「情報」の価値を狙うケースが増えています。
転売目的で本体を盗むだけでなく、個人のプライベートな写真や財務情報、仕事の機密データなどを抜き取り、それをネタに脅迫する、あるいはダークウェブなどで売買するといった二次被害の可能性も考えられます。
高級バッグ・財布
有名ブランドのバッグや財布は、中古市場が確立されており、換金が非常に容易です。
犯人は人気のモデルや状態の良いものを狙って盗み出します。
商品券・ギフトカード
これらは現金同様に扱え、使用時に身分証明も不要なため、犯人にとっては非常に使い勝手の良い盗品となります。
鍵類
意外と見落とされがちですが、家の合鍵や自動車のスペアキーも重要なターゲットです。
合鍵を盗まれれば、犯人はいつでも自由に家に侵入できるようになり、自動車のキーが盗まれれば、車両盗難というさらなる犯罪に繋がる恐れがあります。
一方で、かつては被害の多かったテレビやオーディオ、白物家電といった大型の製品は、搬出に手間がかかり、近隣の住民に目撃されるリスクが高いため、現在では盗まれにくくなっています。
これらのことから、犯人は住居に侵入してからわずか数分という極めて短い時間の中で、いかに効率よく価値のあるものを盗み出すかを常に考えて行動していることが分かります。
そのため、貴重品の保管場所を一箇所にまとめず分散させる、あるいは簡単に持ち出せない重量のある金庫や、床や壁に固定できる金庫を利用するといった対策が有効と考えられます。
また、万が一に備え、高価な品物の写真やシリアルナンバーを控えておくことも、被害届の提出や保険請求の際に役立ちます。
これらは危険!空き巣に入られる前兆

のいぼうラボ イメージ
プロの空き巣犯は、衝動的に犯行に及ぶことは稀です。
その成功の裏には、多くの場合「下見」と呼ばれる周到な準備段階が存在します。
犯人はこの下見を通じて、ターゲットとなる家が「侵入しやすいか(ローリスクか)」「価値のあるものが手に入りそうか(ハイリターンか)」を慎重に見定めているのです。
この偵察活動は、数分間の素早い観察から、数日間にわたって生活リズムを把握する長期的なものまで様々です。
しかし、裏を返せば、この下見の段階こそが、私たちが犯行を未然に防ぐための最大のチャンスでもあります。
犯人が残す、あるいは犯人の行動に現れる些細な「前兆」に気づき、適切に対処することが、我が家を犯罪から守ることに直結します。
マーキング
犯人グループが、下見で得た情報を仲間と共有したり、後で自身が思い出すための目印として、ターゲットの家の敷地内に目立たない印(マーキング)を残すことがあります。
シールの貼り付け
玄関の表札の隅、ポスト、ガスメーターや電気メーターのボックスなど、普段あまり注意を払わない場所に、小さなシールや色付きのテープが貼られているケースです。
一見すると、設備業者が点検で貼ったものと見分けがつきにくいこともあります。
記号の書き込み
油性ペンなどで、小さな文字や記号が書かれていることもあります。
インターネット上では「M(男)」「W(女)」「S(一人暮らし)」「R(留守)」「×(侵入困難)」など、住人の属性や留守の時間帯を示すとされる隠語の存在が語られることがあります。
しかし、これらの意味は犯罪グループによって異なり、信憑性が定かでないものも多いため、記号の解読に固執する必要はありません。
重要なのは「見慣れない印が付けられている」という事実そのものに気づくことです。
もし不審なマーキングを見つけたら、まずスマートフォンなどで写真を撮って記録に残しましょう。
その後、速やかに消去し、念のため警察やマンションの管理会社、大家さんに情報共有することが望ましい対応です。
不審な訪問者や電話
下見の一環として、犯人が住人の在宅状況や家族構成、防犯意識の高さなどを探るために、様々な口実で接触してくることがあります。
業者やセールスを装う
「水道管の無料点検です」「近隣で工事をしていますがご挨拶に」「新しい商品を売りたいのですが」など、もっともらしい理由をつけてインターホンを鳴らし、ドアを開けさせようとします。
その際の応答の仕方や家の中の様子、家族構成などを探っています。
アンケートや道を尋ねるふりをする
家族構成や日中の在宅時間、資産状況などを聞き出そうとしたり、道を尋ねるふりをして親切心につけ込み、家の様子をうかがったりします。
不審な電話
アンケートを装った電話や、無言電話、間違い電話をかけてくることもあります。
これは、電話に出るのが男性か女性か、日中のどの時間帯に在宅しているかなどを探るための手口と考えられます。
身に覚えのない訪問者には、ドアチェーンをかけたまま対応するか、インターホン越しに応対し、安易にドアを開けないことが基本です。
正規の業者であれば、必ず社員証や身分証を携帯しています。
不審に思ったら、その場で会社に電話をかけて正規の訪問かを確認するなど、常に慎重な対応が求められます。
その他の注意すべきサイン
マーキングや直接的な接触以外にも、犯人が残す間接的なサインは日常生活の中に隠されています。
郵便受けの状態
郵便物や新聞、宅配の不在票などがポストに溜まっている状態は、「この家は長期間留守にしている」という明確なサインを犯人に送ってしまいます。
執拗なインターホン
特定の時間に何度もインターホンが鳴らされ、出てみると誰もいない、ということが続く場合、それは単なるいたずらではなく、在宅状況を確認するための「留守確認」である可能性があります。
近所での不審なうろつき
見かけない人物が、特定の家やマンションを繰り返し眺めていたり、車を停めて長時間車内で過ごしていたり、あるいはスマートフォンで話すふりをしながら周囲を観察したりしている場合は、下見を行っている可能性が考えられます。
環境の小さな変化
いつもは閉まっているはずの門扉がわずかに開いている、庭の置物が少し動かされている、といった些細な変化は、犯人が敷地内への侵入のしやすさを試した痕跡かもしれません。
これらの前兆は、一つひとつが必ずしも空き巣に直結するわけではありません。
しかし、複数のサインが重なったり、普段の生活の中で感じる「何かおかしい」という直感は、非常に重要な防犯上の警告です。
少しでも不審に感じたら、それを放置せず、戸締まりを徹底し、近隣の住民と情報を共有して警戒網を築くなど、具体的な行動に移すことが大切です。
空き巣がバレない手口と侵入されたかの確認法

のいぼうラボ イメージ
空き巣犯は、自身の存在を悟られず、かつ犯行が発覚しにくいように、状況に応じて様々な手口を使い分けます。
その手口は年々巧妙化していますが、一方で昔ながらの単純な方法が今なお主流であるという実態もあります。
ここでは、代表的な侵入手口とその詳細、そして万が一被害に遭った際に、侵入されたかどうかを冷静に確認するための方法を詳しく解説します。
犯人が用いる主な侵入手口
警察庁の統計によると、住宅への侵入窃盗で最も多い手口は、高度な技術を要するものではなく、私たちの日常の隙を突く、意外にも単純なものです。
| 侵入手口 | 割合 | 概要 |
|---|---|---|
| 無締り | 52.8% | 施錠されていない窓やドアから侵入する。 |
| ガラス破り | 30.1% | 窓ガラスを破壊して侵入する。 |
| その他 | 17.1% | ドア錠破り、合鍵使用など。 |
参考資料:手口で見る侵入犯罪の脅威
無締り(むじまり)
驚くべきことに、戸建て住宅への侵入の半数以上がこの「無締り」、つまり鍵のかかっていない場所からの侵入です。
犯人にとっては、音を立てる必要も、特殊な道具を使う必要もなく、リスクが限りなくゼロに近い、最も効率的な手口と言えます。
玄関の鍵はもちろん、勝手口や浴室の窓、2階のベランダの窓など、「少しの間だから」「ここからは入らないだろう」といった油断が、犯人にとって絶好の侵入口となります。
ガラス破り
次に多いのが、窓ガラスを破壊して侵入する手口です。これにはいくつかの方法があります。
こじ破り
ドライバーなどを窓とサッシの隙間にねじ込み、てこの原理でガラスに圧力をかけて割る手口です。
焼き破り
ライターや携帯式のガストーチでガラスの一点を熱し、急激な温度変化で音を立てずにひびを入れる巧妙な手口です。
打ち破り
ハンマーなどでガラスを叩き割る原始的な方法ですが、タオルで包むなどして音を小さくする工夫を凝らします。
犯人は大きな音や時間をかけることを嫌うため、窓全体を破壊するのではなく、クレセント錠(窓の鍵)の周辺だけを小さく割り、そこから手を入れて解錠することが多いのが特徴です。
特に、網入りガラスは防犯性が高いと誤解されがちですが、本来は火災時の延焼防止が目的であり、ガラス破りに対しては無力です。
その他の手口
かつて主流だったピッキング(特殊な工具で鍵を開ける)は、防犯性能の高い鍵(ディンプルキーなど)の普及により減少しました。
しかし、ドアにドリルで穴を開けて内側のつまみ(サムターン)を針金などで回す「サムターン回し」や、バールなどでドアをこじ開ける強引な手口も依然として存在します。
侵入されたかを確認する方法
犯行の痕跡を巧みに隠す犯人もいるため、帰宅してもすぐに被害に気づかないケースも少なくありません。
しかし、室内のわずかな「違和感」が、被害を知らせるサインになることがあります。
もし「何かおかしい」と感じたら、パニックにならず、以下の点を冷静に確認してみてください。
玄関周りの確認:
ドアを開ける前に、鍵が普段通りかかっていたか、あるいは不自然に開いていないかを確認します。
ドアノブや鍵穴の周辺に、見慣れない傷やこじ開けようとした痕跡がないか見てみましょう。
窓の状態の確認:
家中の窓を見て回り、施錠したはずの窓が開いていないか、クレセント錠が動いていないかを確認します。
窓ガラスに小さなひび割れや傷がないか、網戸が外れたり破れたりしていないかも重要なチェックポイントです。
室内の違和感の確認:
靴を脱ぐ前に、玄関や廊下に見慣れない足跡がないか確認します。
室内に入り、引き出しやクローゼット、戸棚の扉などがわずかに開いていないかを見てください。犯人は短時間で物色するため、完全に閉めずに立ち去ることがよくあります。
テーブルの上の物の配置、椅子の位置、カーテンの状態など、日常の風景とのわずかなズレがないか観察します。
貴重品の最終確認:
最後に、普段あまり動かさない場所に保管している預金通帳や印鑑、パスポート、宝石類などがなくなっていないかを確認します。
もし、これらの確認作業の中で一つでも明確な異常が見つかり、侵入された可能性が高いと感じた場合は、それ以上室内のものには絶対に触れないでください。
犯人の指紋や足跡、毛髪など、警察の鑑識活動にとって決定的な証拠が残されている可能性があります。
自身の指紋などをつけてしまうと、証拠価値が失われ、捜査を困難にしてしまいます。
直ちに家から出て、ご自身の安全を確保した上で、ためらわずに110番通報することが最も重要です。
通報の際は、慌てずに「空き巣に入られたようです」と伝え、住所と氏名をはっきりと告げてください。
空き巣捕まえ方の基本は事前の防犯対策

のいぼうラボ イメージ
空き巣の被害に遭わないためには、万が一侵入された後に犯人を物理的に捕まえることを考えるよりも、犯人の視点に立ち、「この家は侵入するのが難しい、リスクが高い」と事前に思わせ、犯行そのものを諦めさせることが最も有効かつ現実的な「捕まえ方」と言えます。
その根幹をなすのが、日頃からの周到な防犯対策です。
犯人は常に、最も抵抗の少ない道、つまり最も簡単に入れる家を探しています。
私たちの目的は、その「抵抗」を意図的に作り出し、犯人の計画を初期段階で断念させることにあります。
防犯対策の考え方は、主に「物理的な障壁」と「心理的な圧力」という二つの側面に分けられ、これらを組み合わせることで相乗効果が生まれます。
侵入を物理的に困難にする対策
まず基本となるのは、犯人が家に侵入するまでの時間をいかにして引き延ばすか、という物理的な対策です。
多くの空き巣犯は、人に見つかるリスクを極度に恐れるため、時間のかかる作業を嫌います。
警視庁のデータによれば、侵入に5分以上かかると判断した場合、その約7割が犯行を断念するとされています。
この「魔の5分」をいかに作り出すかが、防御の鍵となります。
ワンドア・ツーロックの徹底
玄関や勝手口など、全てのドアに主錠の他に補助錠を取り付け、鍵を二つにすることが基本中の基本です。
これにより、単純にピッキングなどにかかる時間が2倍になり、犯人の意欲を削ぎます。
防犯性能の高いディンプルキーなど、ピッキングに強い鍵を選ぶことも大切です。
窓の防犯強化
家の侵入経路として最も狙われやすいのは窓です。
特に、大きな掃き出し窓や、死角になりやすい浴室・トイレの窓は重点的な対策が求められます。
防犯フィルム
窓ガラスの内側に強度の高い防犯フィルムを貼ることで、ガラスが割られても飛散せず、穴を開けるのにかなりの時間と労力を要するため、侵入を大幅に遅らせることができます。
補助錠の追加
クレセント錠(窓の鍵)に加えて、サッシの上部や下部に補助錠を取り付ければ、窓をこじ開けることが格段に難しくなります。
防犯性能の高い部品(CP部品)の導入
より高い安全性を求めるのであれば、錠前やドア、窓ガラスといった建具そのものを、防犯性能の高い製品に交換することが推奨されます。
その信頼性の目安となるのが「CPマーク」です。
これは、様々な侵入攻撃に対して5分以上耐えられることが試験で確認された製品にのみ表示が認められる、防犯性能のシンボルです。
犯人の心理に働きかける対策
もう一つの重要な側面は、物理的な障壁だけでなく、犯人に「見られている」「記録されている」「捕まるリスクが高い」という強い心理的なプレッシャーを与え、犯行意欲そのものを削ぐことです。
センサーライトの設置
玄関や裏口、駐車場や庭の死角など、犯人が隠れて作業しそうな場所に、人の動きを感知して自動で点灯するセンサーライトを設置します。
突然の光は犯人を驚かせ、その姿を明るみに出すことで、周囲の住民や通行人の注意を引く効果が期待できます。
防犯カメラの設置
今や防犯カメラは、犯人にとって最も避けたい存在の一つです。
ここで重要なのは、安価なダミーカメラではなく、本物の防犯カメラを設置することです。
プロの犯人は、配線の有無や夜間の赤外線LEDの光り方などで、ダミーを簡単に見破ります。
ダミーだと見抜かれた場合、逆に「この家は防犯意識が低い」というサインを与えかねません。高画質で夜間撮影にも対応したモデルを選び、玄関や窓など侵入経路が映るように設置するのが効果的です。
音による威嚇
犯人は光と同様に、予期せぬ大きな音を極端に嫌います。
防犯砂利
庭や建物の周りに、踏むと「ジャリジャリ」と大きな音が鳴る防犯砂利を敷き詰めることで、隠密に行動しようとする犯人の計画を妨げます。
窓用アラーム
窓の開閉や振動を感知して大音量の警報を鳴らす、安価で設置も簡単なアラームも有効です。
「地域の目」の活用
最もコストがかからず、しかし非常に強力なのが、地域住民による自然な監視の目です。
日頃から近所付き合いを大切にし、挨拶を交わす、地域の清掃活動に参加するなど、コミュニティとの連帯感を高めることが、不審者がうろつきにくい環境を作ります。
犯人は、住民同士の繋がりが強く、「見られている」と感じる地域を避ける傾向にあります。
これらの対策は、どれか一つだけを行えば万全というわけではありません。
物理的な対策と心理的な対策をバランス良く、そして複数組み合わせることで、家の防犯レベルは飛躍的に高まります。
犯人の視点に立ち、彼らにとって「手間がかかる、リスクが高い、魅力のない家」にすることが、結果的に私たちの平和な暮らしを守るための最も確実な道となるのです。
空き巣が捕まらない理由から学ぶべき対策

のいぼうラボ イメージ
この章では、警察の捜査実態と犯人逮捕までの流れを解説します。
その上で、空き巣の被害に遭わないために私たちが今すぐ実践できる具体的な防犯対策を、多角的な視点から紹介します。
ポイント
- 空き巣は捕まらない?知恵袋でのQ&A
- 空き巣で警察は動かない?捜査の範囲とは
- 犯人特定から空き巣が捕まるまでの流れ
- 空き巣の被害に遭わないための具体的な方法
- 総括:空き巣が捕まらない理由と対策の要点
空き巣は捕まらない?知恵袋でのQ&A
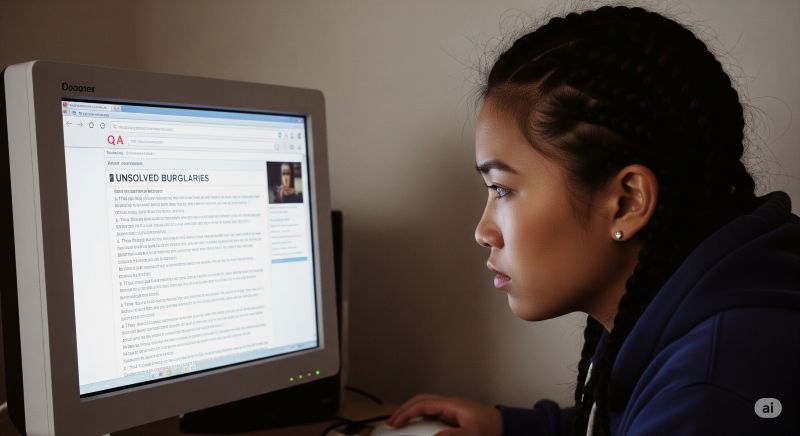
のいぼうラボ イメージ
突然の空き巣被害に遭った後、公式な捜査の進展を待つ間、多くの方が抱える不安や疑問の捌け口として、インターネット上のQ&Aサイト、特にYahoo!知恵袋などを利用するケースが見られます。
これらのサイトは、被害に遭われた方の「今、この瞬間の不安を誰かに聞いてほしい」という切実な気持ちを反映した、デジタル時代の井戸端会議のような役割を果たしていると言えるでしょう。
そこには、被害者の生の声や、それに対する様々な意見が溢れています。
Q&Aサイトに集まる切実な声
サイトを覗くと、被害者の具体的な状況や心情が伝わる、多様な質問が投稿されています。
捜査への不安に関する質問
「警察はきちんと捜査してくれるのでしょうか」「鑑識で指紋が取れなかったと言われました。
もう犯人逮捕は絶望的ですか?」といった、捜査の進展や見通しに対する不安が最も多く見られます。
証拠に関する質問
「防犯カメラに犯人らしき人物が映っていましたが、画質が不鮮明です。
これでも証拠になりますか?」など、手元にある情報がどれだけ有効かを知りたいという質問も目立ちます。
被害品に関する質問
「犯人が捕まっても、盗られたものは返ってこないのでしょうか」「盗品がフリマアプリに出品されていないか毎日探しています。
もし見つけたらどうすればいいですか?」といった、金銭的・精神的な損失の回復に関する質問も切実です。
これらの問いに対し、一般ユーザーや、時には「元警察官」「法律関係者」などを名乗る人物から、様々な回答が寄せられます。
「決定的な証拠がないと難しい」「検挙率は低いのが現実」といった厳しい見方がある一方で、「私の場合は、半年後に犯人が別件で逮捕されて解決しました。
諦めないでください」という希望を持たせるような経験談も投稿されています。
Q&Aサイトの情報の取り扱い注意点
ここで最も重要なのは、これらのQ&Aサイトで得られる情報は、必ずしも正確または客観的であるとは限らないという点です。
玉石混交の情報の中から、何が正しくて何が間違っているのかを個人で判断するのは極めて困難です。
情報の信頼性
回答の多くは、個人の経験や伝聞、あるいは憶測に基づいています。
匿名性の高いプラットフォームであるため、回答者が本当にその分野の専門家であるかを確かめる術はありません。
感情的な意見や、不正確な法律解釈が含まれている可能性を常に念頭に置く必要があります。
誤った情報の危険性
例えば、「警察は窃盗ではあまり動かないから、自分で近所の中古ショップを回った方が早い」といったアドバイスが見られることがあります。
しかし、このような独自調査は、警察の公式な捜査を妨害してしまう可能性がありますし、万が一犯人と接触してしまうような危険も伴います。
精神的な影響
「警察は動いてくれない」といった断定的な書き込みは、被害直後でただでさえ不安な気持ちを、さらに増幅させてしまうことがあります。
一つの否定的な意見が、あたかも全体の総意であるかのように見えてしまい、必要以上に悲観的になってしまう危険性もあるのです。
したがって、これらのQ&Aサイトは、他の被害者がどのような点に不安を感じ、世間一般ではどのように考えられているのか、という「人々の気持ちや関心事の傾向」を知る上では一つの参考になります。
しかし、それを警察の公式な見解や、法的に正確な情報として鵜呑みにするのは絶対に避けるべきです。
空き巣被害に関する正確な情報を得たい、あるいは法的な手続きについて知りたいと考える場合、相談すべき相手はインターネット上の匿名の誰かではありません。
担当の警察官や、必要であれば弁護士といった、責任ある立場の専門家に直接相談することが、問題を解決するための唯一かつ最善の方法です。
空き巣で警察は動かない?捜査の範囲とは

のいぼうラボ イメージ
「空き巣被害を届け出ても、警察は本気で捜査してくれないのではないか」という声や、捜査の進展が見えないことへの不安を時折耳にします。
被害に遭われた直後は警察官が多数訪れ、慌ただしく調査が行われますが、その後ぱったりと連絡が途絶え、忘れられてしまったかのように感じることもあるかもしれません。
これは、被害者にとって捜査のプロセスが見えにくいために生じる、当然の不安と言えるでしょう。
しかし、警察は被害届や被害の通報を受理した場合、必ず法律に基づいた必要な捜査を行います。
「動かない」のではなく、目に見える進展がない「水面下」で、地道な捜査が続けられているケースがほとんどです。ここでは、その捜査の具体的な内容と、なぜ長期化することがあるのかを解説します。
被害届受理後の初期捜査
被害の通報を受けると、警察は迅速に初動捜査を開始します。
この初期段階での活動が、その後の捜査の土台を築きます。
現場臨場と状況聴取
まず、通報を受けて最も早く到着する制服警察官が、被害者の安全を確保し、現場の保全にあたります。
そして、被害者から被害の状況(いつ家を空けたか、帰宅時間、盗まれたものの詳細、不審な点の有無など)を詳しく聞き取り、被害届の作成を補助します。
この聴取内容は、捜査の方向性を決めるための基礎情報となります。
鑑識活動
続いて、私服の刑事や、専門の鑑識係が現場を詳細に調査します。
特殊な粉末や薬品を使って犯人の指紋や掌紋を検出し、静電気を利用して靴跡(足跡)を採取、さらには犯人が残したかもしれない毛髪や繊維、遺留品など、肉眼では見えない微細な証拠もくまなく収集します。
この科学的な捜査は非常に重要で、たとえ小さな証拠も見逃さないよう、丁寧かつ慎重に行われます。
周辺の聞き込み
担当の捜査員は、事件現場だけでなく、その周辺の聞き込み調査も並行して行います。
近隣住民の方々に、事件発生前後に不審な人物や見慣れない車両の目撃情報がなかったか、あるいは不審な物音が聞こえなかったかなどを確認して回ります。
これは、犯人の姿や使用車両を特定するための重要な手がかりとなり得ます。
捜査が長期化する理由と範囲
問題は、これらの丁寧な初期捜査を行っても、犯人特定に直結するような決定的な証拠が得られなかった場合です。
前述の通り、プロの空き巣犯は手袋をするなどして証拠を残さないよう細心の注意を払っているため、有力な物証や目撃情報が得られないケースは少なくありません。
証拠の壁と地道な捜査
指紋などの直接的な証拠がない場合、捜査は「見込み捜査」と呼ばれる、より時間のかかるフェーズに移行します。
例えば、現場周辺の防犯カメラ映像を、自治体や近隣の店舗、個人宅にお願いして提供してもらい、何十時間、時には何百時間もの映像を再生して、犯人らしき姿を探します。
また、過去に同じような手口( modus operandi)で検挙された人物のリストを洗い直したり、盗まれた品物の特徴を全国の質屋やリサイクルショップに手配し、犯人が換金に現れるのを待ったりと、地道な捜査が続けられます。
捜査資源の限界
警察は、空き巣事件だけでなく、殺人や強盗、詐欺といった、社会を震撼させる様々な事件に日々対応しています。
限られた人員と予算の中で、全ての事件に無限の捜査員を投入することは現実的に不可能です。
もちろん、だからといって空き巣の捜査を軽視するわけではありません。
しかし、客観的な証拠が乏しく、新たな手がかりが見つからない事件では、別の事件で犯人が逮捕された際に余罪として発覚するのを待つなど、捜査が長期化し、結果として被害者からは「停滞している」ように見えてしまうことがあるのです。
「警察が動かない」と感じられる背景には、こうした捜査の構造的な困難さが存在します。
捜査の範囲は、得られた証拠や情報に応じて決まります。
被害者としては、後からでも「そういえばあの日、見慣れない車が停まっていたな」といった些細なことでも思い出したことがあれば、ためらわずに担当の警察署に情報提供することが、捜査を思わぬ形で進展させる一助となる可能性があります。
犯人特定から空き巣が捕まるまでの流れ

のいぼうラボ イメージ
地道な捜査活動によって、散らばっていた証拠や情報というパズルのピースが繋がり始め、一人の容疑者が捜査線上に浮かび上がった場合、捜査は犯人逮捕、すなわち「検挙」という最終段階へと向かいます。
この犯人が特定されてから逮捕され、法的な手続きに乗るまでには、緻密な証拠の積み重ねと、厳格な法的手順が必要となります。
容疑者の特定
まず、警察は集めたあらゆる情報を分析し、容疑者を一人に絞り込んでいきます。
特定に至るルートは、主に以下のパターンに分けられます。
証拠による特定
これは最も確実なルートです。
現場に残された指紋や掌紋を警察の自動指紋識別システム(AFIS)で照会し、過去に犯罪歴のある人物のデータと一致した場合、容疑者はほぼ確定します。
同様に、現場で採取された血液や毛髪などのDNAが、データベース上の特定の人物と一致した場合も、極めて強力な証拠となります。
捜査線上の浮上
直接的な物証がない場合でも、多角的な捜査によって容疑者が浮かび上がることがあります。
防犯カメラ映像の追跡
現場周辺のカメラから、犯人らしき人物や車両を特定し、その移動ルートを何十台ものカメラ映像を繋ぎ合わせて追跡します。
これにより、人物の立ち寄り先や、車両のナンバープレートから所有者を割り出していきます。
盗品の追跡
警察は、被害品リストを全国の質屋や古物商に手配します。
古物営業法に基づき、買取店は売主の身元確認と記録が義務付けられているため、犯人が盗品を換金しようとすれば、そこから足がつくことがあります。
共犯者や関係者からの供述
別の事件で逮捕された人物が、余罪として空き巣を自供したり、その仲間に関する情報を提供したりすることで、新たな容疑者が浮上するケースも少なくありません。
逮捕状の請求と執行
容疑者が特定され、その人物が犯人であると疑うに足りる相当な理由と客観的な証拠が揃った段階で、警察は「逮捕」という強制的な手続きに移行します。
ただし、そのためには中立的な司法の判断を仰がなければなりません。
警察は、これまでの捜査で集めた証拠をまとめ、裁判官に対して逮捕状を請求します。
裁判官は、その証拠を基に「逮捕の理由(犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由)」と「逮捕の必要性(被疑者が逃亡したり、証拠を隠滅したりする恐れ)」を慎重に審査します。
この審査を経て、逮捕状が発付されて初めて、警察は容疑者を逮捕することができるのです。
逮捕状が執行される際は、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐため、早朝に自宅を訪れるなど、不意を突く形で行われることが一般的です。
これが、いわゆる「通常逮捕」です。
一方、犯行の真っ最中や直後に身柄を確保する「現行犯逮捕」の場合は、逮捕状は不要とされています。
余罪の追及と送検
空き巣犯の多くは、一度だけでなく、常習的に犯行を繰り返している場合があります。
そのため、警察は被疑者を逮捕した後、その人物が関与した可能性のある他の未解決事件がないか、すなわち「余罪」について厳しく追及します。
被疑者の自宅などを捜索し、他の被害品が見つかったり、自供を引き出したりすることで、次々と余罪が明らかになっていきます。
実は、統計上の検挙率が押し上げられる背景には、この「余罪捜査」が大きく関わっています。
一人の常習犯が逮捕されることで、その犯人が関与した数十件の未解決事件が一挙に解決(検挙)されることがあり、これが全体の検挙数を大きく引き上げているのです。 出典:法務省 令和4年版 犯罪白書
逮捕後、警察は48時間以内に、捜査資料や証拠品と共に被疑者の身柄を検察官に送致します(送検)。
その後、検察官は24時間以内に、さらに身柄を拘束して捜査を続ける必要があるかを判断し、必要であれば裁判官に勾留を請求します。
勾留が認められると、原則10日間、最大で20日間身柄が拘束され、その間に検察官が起訴するかどうか(不起訴処分とするか)を最終的に決定します。
このように、一人の犯人が逮捕され、裁判に至るまでには、地道な証拠収集から、複数の法的な関門をクリアしていく、長く複雑なプロセスが存在しているのです。
空き巣の被害に遭わないための具体的な方法

のいぼうラボ イメージ
これまでの分析を踏まえ、空き巣の被害という不幸な出来事を未然に防ぐために、今日からでも実践できる具体的な防犯対策を多角的に紹介します。
完璧なセキュリティというものは存在しませんが、重要なのは複数の対策を「層」のように組み合わせ、犯人にとっての侵入のハードルを総合的に引き上げることです。
犯人の視点に立ち、「この家は面倒だ、リスクが高い」と思わせることができれば、彼らは自らターゲットから外していきます。
住宅の物理的な防御力を高める
まず、基本となるのは、犯人の侵入を物理的に困難にし、時間をかけさせることです。
犯行に時間をかければかけるほど、発覚のリスクは高まります。
この時間的障壁をいかにして作るかが、物理的防御の核心です。
全ての出入り口の施錠を習慣化する
「ゴミ出しだけだから」「2階の窓だから大丈夫」といった油断が、最大の脆弱性となります。
プロの空き巣犯は、わずか数分の隙も見逃しませんし、2階へも雨どいや足場を利用して容易に登ります。
外出時、就寝時はもちろん、在宅中であっても普段使わない部屋の窓は必ず施錠する、ということを家族全員のルールとして徹底しましょう。
補助錠を取り付け、防御点を増やす
玄関や勝手口に主錠の他に補助錠を設置し、「ワンドア・ツーロック」にするのは非常に有効です。
これにより、解錠にかかる時間は単純に2倍以上になり、犯人の意欲を大きく削ぎます。
同様に、最も侵入経路となりやすい窓にも、クレセント錠だけでなく、サッシの上部や下部に取り付けるタイプの補助錠を追加し「ワンウィンドウ・ツーロック」を心掛けましょう。
防犯フィルムや防犯ガラスで窓を強化する
ガラス破り対策として、窓ガラスの内側に強度の高い防犯フィルムを貼ることは極めて効果的です。
これはガラスを割れなくするものではなく、割られてもフィルムがガラスの破片を保持し、穴を開けるのに多大な時間と労力を要させるためのものです。
大きな破壊音が出続けるため、犯人は途中で犯行を断念せざるを得なくなります。
より高いレベルの対策として、新築やリフォームの際には、2枚のガラスの間に特殊な膜を挟んだ「防犯合わせガラス」の導入も検討する価値があります。
面格子の強度を点検・補強する
お風呂場やトイレ、キッチンの窓などによく設置されている面格子ですが、これが意外な盲点となることがあります。
取り付けネジが短い、あるいは外から簡単に外せる構造のものが多く、犯人にやすやすと突破されてしまうケースが後を絶ちません。
定期的にネジが緩んでいないか、格子自体にぐらつきがないかを確認し、必要であればネジを長くしたり、外側から外せない特殊なネジに交換したりする補強が大切です。
犯行をためらわせる心理的な対策
物理的な障壁に加えて、犯人の心理に「見られている」「記録されている」「音で気づかれる」というプレッシャーを与え、犯行そのものをためらわせる環境を作ることも同等に重要です。
防犯カメラやセンサーライトを「見せる」設置
これらの機器は、犯行の抑止が第一の目的です。
そのため、隠すのではなく、あえて目立つ場所に設置し、「この家は監視されている」と犯人に明確にアピールすることが肝心です。
センサーライトは玄関や裏庭、通路などの死角を照らすように、防犯カメラは侵入経路となるドアや窓がはっきりと映るように設置しましょう。
「音」で犯人を威嚇する
犯人は物音を立てて周囲の注意を引くことを極端に嫌います。
家の周りの死角になりやすい場所に、踏むと大きな音が鳴る「防犯砂利」を敷き詰めるのは、安価で効果的な対策です。
また、窓やドアの開閉・振動を感知して大音量で威嚇する防犯アラームも、犯人を驚かせ、撃退するのに役立ちます。
タイマー付き照明で在宅を偽装する
旅行などで長期間家を空ける際、家の中が常に真っ暗だと、不在であることの何よりの証拠になってしまいます。
タイマー付きの照明やスマートプラグを活用し、夜間にリビングや寝室の明かりが自動で点灯・消灯するように設定しておけば、あたかも人が中にいるかのように装うことができます。
ラジオやテレビをタイマーでつけるのも効果的です。
「地域の目」という最強の監視網を築く
日頃から「おはようございます」「こんにちは」と挨拶を交わし、ご近所との良好なコミュニケーションを築いておくことは、非常に強力な防犯対策となります。
住民同士の連帯感が強い地域は、不審者がうろつきにくく、下見の段階で犯行を諦めさせます。
長期で家を空ける際には隣近所に一声かけておけば、郵便物の管理をお願いしたり、何か異常があった場合に通報してもらえたりと、互いに助け合うことができます。
日常生活での注意点
最新の防犯設備を導入しても、日々の何気ない行動が犯罪のきっかけになることがあります。
SNSの利用には最大限の注意を払う
「来週からハワイ旅行!」といった未来の予定や、旅行先からのリアルタイムな写真投稿は、「私の家は今、留守ですよ」とインターネット上で世界中に公言しているのと同じです。
楽しい思い出の共有は、必ず帰宅してから行うようにしましょう。
また、アカウントのプライバシー設定を「友達のみ」に限定するなど、個人情報が不特定多数に漏れないよう管理することが不可欠です。
郵便物やゴミ出しで生活を悟らせない
長期不在時に新聞や郵便物がポストに溜まっている状態は、不在のサインそのものです。
必ず配達を一時停止する手続きを取りましょう。
また、高価な家電などを購入した際、その空き箱を無造作にゴミ捨て場に出すと、「この家には価値のあるものがある」と宣伝しているようなものです。
箱は細かく解体して中身が見えないようにするか、直接処理施設に持ち込むなどの配慮が望まれます。
これらの対策は、どれか一つだけを行えば万全というわけではありません。
「施錠」という基本を徹底した上で、ご自身の住まいの状況やライフスタイル、予算に合わせて、物理的な対策と心理的な対策をバランス良く、そして複数組み合わせて実践していくことが、大切な家と財産を空き巣被害から守るための最も確実な鍵となるのです。
総括:空き巣が捕まらない理由と対策の要点
この記事では、空き巣が捕まりにくい理由とその対策について、多角的に解説してきました。
最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。
記事のポイント まとめです
- 空き巣は家人の留守を狙う計画的な侵入窃盗である
- 侵入窃盗の検挙率は約5割で推移している
- 犯人が捕まるかどうかは事前の対策にかかっている
- 最も多い侵入手口は施錠忘れによる「無締り」である
- 現金や貴金属など換金しやすいものが主に狙われる
- 犯行前にはマーキングなどの「前兆」が見られることがある
- 侵入の痕跡が少ない巧妙な手口も存在する
- 被害に気づいたら現場を維持しすぐに110番通報する
- 防犯対策は物理的な防御と心理的な抑止を組み合わせる
- 犯人は侵入に5分以上かかると諦める傾向がある
- ワンドア・ツーロックは防犯の基本である
- 警察は被害届を受理すれば必ず捜査を行う
- 証拠が少ないと捜査が長期化する可能性がある
- SNSでのリアルタイムな情報発信はリスクを伴う
- 「地域の目」は非常に有効な防犯対策である
参考情報一覧
- 警察庁公式サイト: https://www.npa.go.jp
- 法務省 犯罪白書: https://www.moj.go.jp/housouken/housouken_housouken03.html
- 警視庁 住まいる防犯110番: https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki26/
- 政府広報オンライン: https://www.gov-online.go.jp
- SECOM株式会社 防犯・セキュリティコラム: https://www.secom.co.jp/homesecurity/bouhan/
- ALSOK(アルソック) 防犯対策: https://www.alsok.co.jp/person/recommend/
- 日本ロックセキュリティ協同組合: https://www.jalose.org
- ベリーベスト法律事務所 刑事事件専門チーム: https://www.vbest.jp/criminal/
- Yahoo!知恵袋: https://chiebukuro.yahoo.co.jp
- PR TIMES (株式会社 PR TIMES): https://prtimes.jp
/関連記事 「もしかして、空き巣…?」そう感じた時、いつ入られたか全くわからない状況は、大きな不安と恐怖を伴います。 そもそも空き巣って何ですか?という基本的な疑問から、空き巣に入られたか確認する方 ... 続きを見る 「ピンポーン」と鳴ったインターホン。「部屋を間違えました」と言われて、少し不審に思った経験はありませんか。 その訪問、本当にただの間違いでしょうか。 実は、部屋間違いインタ ... 続きを見る

関連記事空き巣にいつ入れたかわからない?初動と対策の完全ガイド

関連記事空き巣対策!「インターホン間違えました」は危険なサイン

